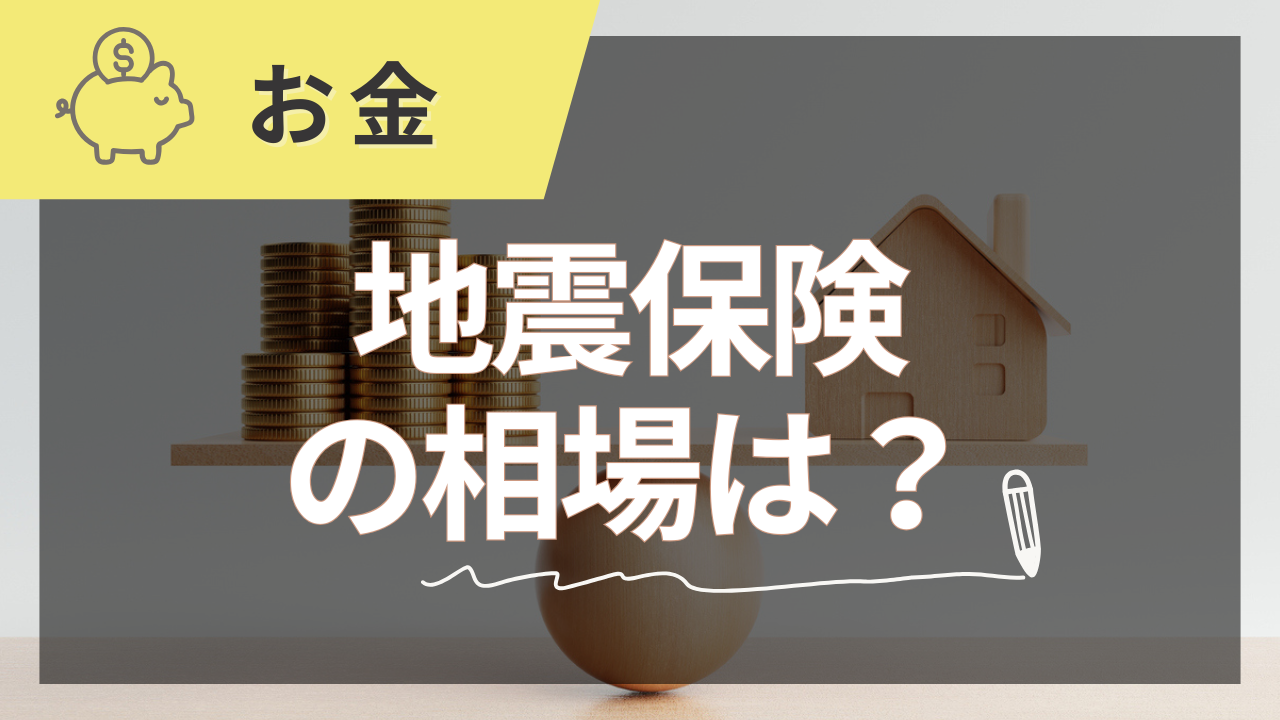地震保険の相場を左右する主な要因
地域と震度リスク区分で保険料はどう変わるか
地震保険の保険料は、全国を四つに分けた「地震保険料率区分」に基づき算出されます。最もリスクが高い区分1(関東・東海エリア)では保険料率が突出して高く、同じ建物でも区分4の北海道内陸部と比べて約2倍になるケースも珍しくありません。実際、東京都心の延べ床面積100㎡の木造住宅で設定額1,500万円の場合、地震保険料は年間約4万円台後半ですが、北海道帯広市なら2万円台前半に収まります。
加えて、自治体公表の地震ハザードマップが保険会社の内部リスク評価に活用される流れも加速しており、従来は同一区分だったエリアでも細分化で料率が変動し始めています。引っ越しや建て替えを検討する際は、地盤や活断層だけでなくエリア区分の推移も確認することで、長期的な保険コストを抑えられる可能性があります。
建物構造・築年数による料率差の実態
建物構造は「耐火」「非耐火」の二分類が基本で、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)は耐火建物として料率が安く設定されています。たとえば同じ首都圏でも、築浅のRCマンションと築30年の木造戸建てでは、年間保険料にして1万円以上の差が生じることもあります。
さらに築年数10年を境に保険金受取時の時価評価が急激に下がる点も見逃せません。築古物件はそもそもの評価額が低いため保険料は抑えられますが、地震発生後に再建費用が不足するリスクが高まります。元トップセールスマンの私の経験上、築15年以上の木造戸建てでは、耐震補強を先に行うことで保険料だけでなく命も守れる実益が大きくなりました。
保険金額と免責設定がコストに与える影響
地震保険は火災保険の30〜50%範囲内で保険金額を設定します。上限いっぱいに設定すると安心感は高まりますが、保険料も大幅にアップします。一方、免責金額を5万円や10万円に設定すれば保険料は下がりますが、小損害時に自己負担が生じる点を理解しておく必要があります。
おすすめは「生活再建に必須となる最低額+家財分」を目安に保険金額を設定し、免責は0円に近いプランを選ぶことです。これなら大規模地震での生活立て直しがスムーズで、コスト負担も無理なく調整できます。まずはご自宅の評価額とライフスタイルを照らし合わせ、必要保障額を試算してみましょう。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。

地域・建物別に見る地震保険料シミュレーション
首都圏マンションで試算する相場の目安
首都圏の耐火構造マンション(専有面積70㎡、築5年)で、火災保険金額1,400万円・家財500万円と想定すると、年間地震保険料は約2万9千円前後が目安です。ここには「建物」9:「家財」1の割合でリスクを設定する考えが反映されており、家財を下げても削減効果は限定的です。
保険会社ごとの割引制度を適用すると、長期(5年)一括払いや免震構造割引で最大30%近い割引を受けられるケースもあります。特に免震マンションは料率が優遇されるため、購入価格が高くてもランニングコスト面で得をする可能性があります。新築・中古問わず検討の際は、管理会社に免震・制震データの有無を確認しておくとよいでしょう。
木造一戸建て(地方都市)の保険料シナリオ
地方都市に多い在来木造2階建て(延べ床100㎡、築3年)で、火災保険2,000万円・家財1,000万円を上限設定すると、地震保険料の目安は年間4万3千円前後となります。首都圏より地震リスク区分が低い地域でも、木造は非耐火扱いとなることで料率が上がる点が主因です。
ここで注目したいのが「省令準耐火住宅」の認定取得。外壁と軒裏を不燃材にするなどの仕様で、木造でも耐火建築物として扱われ、料率が耐火構造並みに下がります。新築時に追加コスト数十万円で認定を受けると、地震保険料のほか火災保険料も通算で大幅に節約できるので、将来の保険料負担まで視野に入れて住宅仕様を決めることが重要です。
賃貸オーナーが押さえるべき保険料相場
投資用物件や賃貸併用住宅を保有するオーナーの場合、建物全体にかける地震保険と各入居者が加入する家財保険を切り分けて考える必要があります。鉄骨3階建てアパート(延べ床300㎡)で保険金額6,000万円とした場合、年間保険料は約40万円が目安となりますが、長期一括契約や複数棟一括割引で10〜15%下げられるケースが大半です。
また、入居者向け家財保険に地震補償をセットすることで、自然災害による退去リスクを低減できるメリットもあります。オーナーが主体的に保険プランを比較し、管理会社まかせにしない姿勢こそが、長期で安定した賃貸経営を実現する鍵となります。ここで得た目安を、今すぐ家計シートや収支計画に反映してみませんか。
補償内容と免責の仕組みを理解しよう
全損・半損・小半損・一部損の判定基準
地震保険の支払いは「全損・大半損・小半損・一部損」の四段階で判定され、建物や家財の損害割合によって支払額が決まります。たとえば建物の主要構造部の損害額が50%以上なら「全損」と見なされ、保険金額の100%が支払われます。一方20%未満の損害は一部損となり、保険金額の5%しか支払われません。
この判定基準は、阪神・淡路大震災で支払いが長期化した反省から、写真判定と現地調査を組み合わせて迅速に決定されるよう改善されています。とはいえ部分損に該当した場合は自己資金が不足しがちなので、免責金額を低めに設定しておくか、生活再建費用を別途確保する工夫が不可欠です。
家財補償は必要?選び方と費用感
家財の損害は、家具転倒や火災による焼失で生活基盤を直撃するため、建物以上に迅速な資金手当てが求められます。家財補償は世帯人数に応じた目安額が公表されていますが、実情に合わせて調整することが重要です。たとえば共働き夫婦2人暮らしなら400万円前後で十分でも、小学生と中学生の子どもがいる4人家族なら700万円前後は確保したいところです。
家財補償を手厚くすると保険料は上がりますが、保険会社によっては家財料率が割安な商品もあるため比較が必須です。私は営業時代、顧客の家財リストを写真と併せて保存するシンプルな方法を提案し、後の保険金請求でスムーズに実額査定できた事例を多数見てきました。家族で所有物を棚卸しする機会として活用してみてください。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。
免責金額の設定でトータルコストがこう変わる
免責金額を1回あたり5万円に設定すると保険料はおおむね5〜8%下がりますが、小規模損害では保険金ゼロになる事態もあり得ます。逆に免責を0円にすると保険料は上がりますが、突発的な損害にも即対応できます。ポイントは「水漏れや落雷など日常リスクには火災保険、地震による大損害には地震保険」という二段構えです。
トータルコストを抑えつつ安心感を確保するには、免責0円+省令準耐火割引+長期契約割引を組み合わせるのが鉄則です。内容を理解したら、ご家族とも話し合い、必要な補償をメモに書き出してみてください。

地震保険料を節約する7つのプロのテクニック
耐震診断・省令準耐火・長期契約割引の活用法
最もインパクトが大きいのは、自治体補助を活用した耐震診断と補強工事です。耐震等級3を取得すれば、料率が最大50%以上下がる上、地震での倒壊リスクも大幅に減少します。省令準耐火仕様も同様に割引対象となり、木造でも鉄骨並みの料率が適用されます。
また、5年長期一括契約は年払いと比べて6〜8%の割引を受けられる点が見逃せません。長期で資金を固定できるか不安に感じる方もいますが、途中解約でも残存期間分の保険料は返戻される仕組みなのでご安心ください。加入時は必ず長期見積りを取り寄せ、差額を具体的な数字で比較しましょう。
火災保険とのセット加入で得られる複合割引
火災保険と地震保険はセット加入が原則ですが、近年は水災や破損・汚損補償をパッケージに組み込み、トータル料率を下げる商品が増えています。たとえば水災リスクが低い高台エリアでは、水災補償を外す代わりに地震保険を手厚くするといった柔軟な設計が可能です。
重要なのは「補償の重複と不足を同時に点検する」こと。補償が重複しているのに気づかず保険料を払い過ぎているケースは年間数万円規模で存在します。各補償の範囲を一つずつ可視化し、不要な特約をカットすることで、毎月の保険料にゆとりが生まれます。
保険代理店とネット保険を比較して最安プランを探す
保険代理店は対面で相談できる安心感がありますが、ネット専業保険は固定費が低いため料率の割引余地が大きくなります。特に若年層の単身世帯や共働き家庭では、ネット申込限定の割引を活用することで、年間数千円〜1万円の保険料差が出ることも少なくありません。
ただし、いざ地震が起きた際のサポート体制は代理店型が優勢です。そこでおすすめなのが、保険料が高い代理店型と安いネット型の見積書を並べ、補償範囲とサポート内容を一覧化する方法です。比較検討のプロセス自体が、家族会議で保険理解を深める貴重な機会になります。一つでも実践できそうなテクニックがあれば、今日から動き始めましょう。
加入前にチェック!よくある失敗とその回避策

加入前に確認すべき5つの書類と情報
地震保険を申し込む際には、建物登記簿謄本、建築確認済証、耐震等級証明書、火災保険証券、ハザードマップの5つが必須書類・情報となります。これらを事前に揃えておくことで、保険会社の審査がスムーズに進み、見積もりの齟齬も防げます。
私が担当したお客様で、建築確認済証が見当たらず手続きが2週間遅れ、ちょうどその間に地震が発生したというケースがありました。幸い大きな被害はありませんでしたが、書類不足が家計と安心を揺るがすリスクになると痛感したエピソードです。
補償不足で泣いたケーススタディ
補償不足は「思ったより保険金が出なかった」だけでなく、ローン残債をカバーできず自己破産に追い込まれる深刻な事態を招く可能性があります。熊本地震では、築10年未満でも全損判定を受け、建築費高騰で再建費用が保険金を大幅に上回ったケースが多数報告されました。
補償不足を防ぐには、建物再調達価額を定期的に見直し、物価上昇や建築コストを反映させることが不可欠です。加えて、追加借入が必要になったときに備え、住宅ローン特約付地震保険や団信上乗せ補償を検討することで、家計破綻リスクを減らせます。
過剰補償で保険料を無駄にした事例と改善ポイント
反対に過剰補償の典型例は、築30年以上の木造住宅に再調達価額ベースで上限いっぱいを設定しているケースです。時価評価との差額分は保険金として受け取れず、無駄な保険料を払い続ける結果になります。
改善の第一歩は、耐用年数と残価を客観的に評価し、実際に必要な生活再建費用に合わせて保険金額を減額することです。また、家族構成やライフステージの変化に合わせて、家財補償を段階的にスリム化する方法も効果的です。加入手続き前に、チェックリストを手元に置いて確かめてみてください。
2025年以降の料率改定動向と将来予測
最新の料率改定ポイントとその背景
損害保険料率算出機構は、2025年7月に発表した最新料率で、耐火・非耐火別の格差をさらに拡大しました。背景には、南海トラフ巨大地震の長期評価見直しと、首都直下地震リスクの再計算結果が反映されています。これにより、首都圏の非耐火住宅では平均7.2%の保険料上昇が見込まれ、保険料の地域差が今まで以上に家計を圧迫する可能性があります。
ただし、省令準耐火や免震構造などの割引制度も同時に拡充されており、リスク削減努力が保険料削減に直結する設計になった点は大きな進歩です。リフォームや建て替えの際は、料率改定の方向性を踏まえた長期プランニングが求められます。
AIによるリスク細分化で保険料はどう変わるか
AI技術の進展により、保険会社は従来の大まかな区分ではなく、ピンポイントで住所単位の地盤・建物情報を元に保険料を算出する動きが強まっています。これは大手地図情報会社のデータと連携し、30m四方のメッシュごとにリスクを評価する仕組みで、低リスク地域は保険料が実質値下がり、高リスク地域は上昇という傾向が鮮明になりつつあります。
ユーザー側のメリットは、耐震補強や免震改修の投資効果が保険料に即反映される点です。一方、高リスク地域に住む場合は自己負担が増える可能性があるため、事前にハザードマップだけでなく保険会社の試算ツールで確認しておくと安心です。
今こそ地震保険を見直すべきタイミングとは
料率改定と細分化が進む2025年は、地震保険を見直す絶好のタイミングです。長期契約を組んでいる方も、契約途中での増減額や期間短縮は可能なので、建物評価額の見直しと併せて保険プランを最適化しましょう。
特に物価上昇が続く現状では、再建費用不足リスクが高まっています。必要に応じて保険金額を増額しつつ、割引制度を漏れなく適用することで、コストと補償のバランスを整えられます。改定情報が出たらすぐに見直せるよう、通知設定をしておきましょう。
地震保険を味方につけて、安心のマイホーム計画を

家づくりを始めると、気になることが次々と出てきます。
ネットで情報を調べても、「これって本当に正しいの?」「うちに合ってるのかな?」と、かえって不安になる方も少なくありません。
そんな悩みに寄り添うために、私たちはNo.1住宅プランナーと、家づくりを経験した先輩ママたちと一緒に、「日本一信頼できる家づくりプラットフォーム」をつくりました。
▼後悔のない家づくりのために、まずは気になることから、ゆっくり見てみませんか?