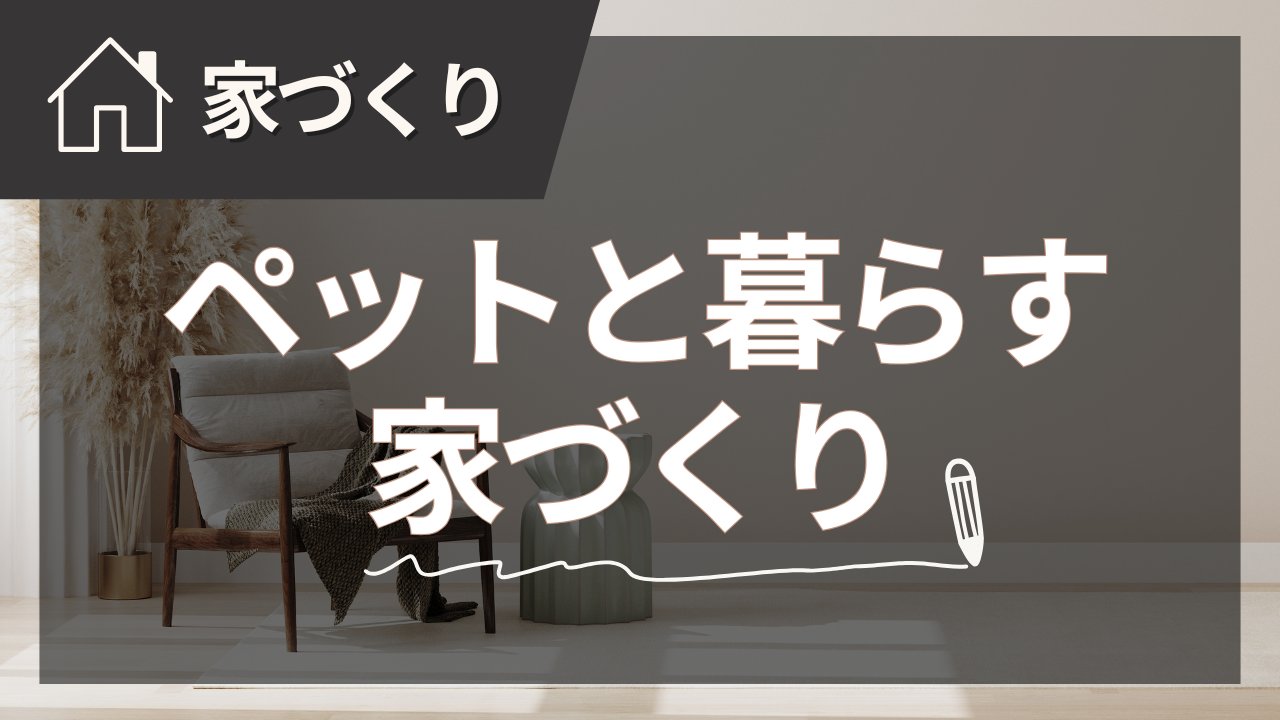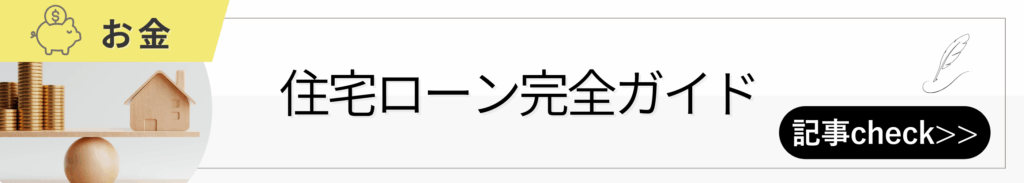ペットと人の両方が快適に暮らす家とは?
ペットと暮らす家を考える際に重要なのは、単なる「ペット可住宅」ではなく、ペットも人もストレスなく共生できる空間づくりです。家は単に住む場所ではなく、日常の安心や癒しを感じる場所であり、その主役にペットがいる家庭では、その子の存在を前提とした設計が求められます。
たとえば、猫なら上下運動がしやすいキャットウォークや棚の設置、犬であれば散歩帰りに足を洗える専用の洗い場や、室内トイレスペースの設置が考えられます。人の動線とペットの動線がぶつからないようにすることで、日々の暮らしのストレスを減らすことができます。
さらに、ペットが安心できる居場所を確保することも大切です。騒音や来客のストレスを避けるために、静かで落ち着けるスペースや、視線を遮る工夫などが求められます。ペットも家族の一員として尊重し、環境面での配慮を積み重ねることが、真に快適な住まいにつながります。
ペットが安心し、家族が笑顔で暮らせる住まいを一緒に考えてみましょう。

ペット共生型住宅のニーズが高まる理由
少子高齢化や単身世帯の増加などを背景に、ペットを家族とする暮らしが増えています。ペットは「癒し」や「安心感」の存在であり、その生活に配慮した家づくりのニーズは年々高まっています。
住宅展示場では「ペットと暮らす家」をテーマにしたモデルハウスが登場するなど、住宅業界においても新たなマーケットとして注目されています。とくに新築戸建てやリノベーションの検討段階で、ペット目線での間取り設計・素材選びを希望する相談が増えているのが実情です。
また、ペットとの暮らしは人の健康や幸福度にも好影響を与えることが多く、共生型住宅は「心の健康を支える家」としても注目されています。ペットのためにと考えた設計が、結果的に子育てや老後の安心につながるケースもあります。
今後ますます多様化する家族の形に対応するためにも、「ペットと暮らす家」は現代の家づくりに欠かせない選択肢となっていくでしょう。
家づくり前に考える「ペットとの暮らし方」
犬・猫・小動物…ペット別に変わる設計の考え方
ペットの種類によって、家づくりで気をつけるポイントは大きく異なります。犬は活動的で屋外との行き来が多く、猫は高いところへの移動を好みます。うさぎやハムスターなどの小動物は静かな環境と安全性が求められます。
犬の場合、散歩からの帰宅後に足を洗える場所や、汚れを落としやすい床材が必須です。また、玄関や門からの脱走を防ぐためのゲートやフェンスの設計も重要です。室内では、人との接触を適度に保てる位置に寝床を配置することで安心感を与えられます。
猫の場合は、上下運動ができる立体的な空間設計がポイントです。キャットウォークや階段の構造を利用した遊び場があると、ストレスのない生活環境になります。また、日当たりのよい窓辺や隠れ家になる小スペースも重視されます。
小動物は振動や音に敏感なため、生活動線から離れた静かな部屋を用意し、床材や空調の配慮も必要です。適切な湿度管理も健康に影響します。
ペットの性質を理解し、その子に合わせた設計が、長く安心して暮らせる家をつくる第一歩です。
ライフステージごとに変わる飼い主のニーズ
家づくりは、今の暮らしだけでなく、将来の変化を見据えて計画することが求められます。特にペットと暮らす場合、その配慮は飼い主のライフステージと深く関係しています。
たとえば、子育て世代であれば、子どもとペットの安全な共存がテーマになります。リビングにペットと子どもが安心して過ごせるエリアをつくる工夫や、玄関・階段にゲートを設置するなどの安全対策が重要になります。
一方、シニア世代では、自身の体力の変化やペットの高齢化も見据えた設計が必要です。段差の少ないバリアフリーな間取り、掃除のしやすさ、病院へのアクセスのしやすさなど、生活負担を減らす工夫が求められます。
また、将来ペットを飼う予定がある場合でも、事前に配慮した設計を取り入れておくことで、後からの工事を減らし、コストやストレスを抑えることができます。
家族構成やライフスタイルの変化に柔軟に対応できる家づくりを意識することが、ペットとの暮らしを豊かにする鍵になります。

ペットと暮らすおすすめ間取り
ペットのストレスを軽減する動線設計とは
ペットにとっても「暮らしやすい動線」は重要です。犬や猫は自分のテリトリーを持ち、一定のルートを好んで移動します。そのため、人の生活動線とペットの行動動線がぶつからないように設計することで、お互いにストレスを感じにくくなります。
たとえば、リビングと寝室をつなぐ廊下にペット専用の通路をつくったり、引き戸を採用して静かに出入りできるようにするなどの工夫があります。また、ペットが安心して休める場所を動線の先に配置することで、リラックスできる環境をつくれます。
玄関からキッチン、洗面所まで一直線の動線があると、散歩帰りの足洗いや食事の準備、トイレ掃除などの作業も効率的になります。加えて、トイレや餌場の近くには換気扇や窓を設けることで、においや湿気の対策にもつながります。
人とペットの行動パターンを丁寧に洗い出し、ぶつからない・邪魔しない・動きやすい間取りを設計することが、快適な生活空間をつくる鍵となります。
ペット専用スペースの考え方と配置ポイント
ペット専用スペースを設けることは、安心感と自立心を育てるうえで非常に有効です。ただし、単なる「囲い」ではなく、ペットが落ち着ける場所としての機能性と、家全体のインテリアになじむデザイン性の両立が求められます。
設置場所としておすすめなのは、人の気配を感じつつも静かに過ごせる場所です。たとえばリビングの一角や階段下のデッドスペース、寝室の隅などが人気です。直射日光を避け、空調の風が直接当たらない場所を選ぶことで、ペットにとって快適な環境になります。
また、クレートやケージを使う場合は、インテリアと調和するデザインを選び、収納棚と一体化するなどの工夫をすると空間を有効活用できます。床材や下地には、掃除のしやすい素材や滑りにくい仕上げを選ぶと安心です。
犬や猫の性格や体格、年齢に応じて、囲いの高さや素材を調整することも大切です。音や光を遮断する小屋型、自由に出入りできるオープンタイプなど、ペットの好みに応じた設計が理想です。
ペット専用スペースを設けることで、家全体の秩序が保たれ、ペットにも安心感を与えることができます。
キッチン・トイレ・寝室のペット対策アイデア
家の中でトラブルが起きやすいのが、キッチン、トイレ、寝室といった「生活のコアエリア」です。これらの空間にはペットとの共存にあたって、特別な配慮が必要になります。
まずキッチンでは、火や刃物、ゴミなどの危険物が多く、ペットの侵入は極力避けたいエリアです。ペットゲートや引き戸で侵入を防ぐのが基本ですが、床の滑りやすさにも注意が必要です。さらに、収納棚の扉はロック式にし、誤飲防止を徹底しましょう。
トイレについては、人用とペット用のゾーニングを明確にすると、においや衛生管理のしやすさが格段にアップします。ペット用トイレは目立たず、換気のしやすい場所に設置するのが理想的です。来客時に見えにくい工夫も快適な空間づくりにつながります。
寝室にペットを入れるかどうかは家庭によって異なりますが、共に寝る場合はベッドの高さや足元の安全確保が重要です。ベッド下に入り込まないよう柵をつけたり、落下防止のステップを設けたりすることで、安全性を高められます。
生活の中心となる空間だからこそ、ペットとの暮らしを想定した設計が求められます。

ペットと暮らす家づくりで選びたい素材と設備【ペット配慮型】
滑りにくい床・傷がつきにくい壁材の選び方
ペットと暮らす住まいにおいて、「素材選び」は安全性と快適性の両面で大きなカギを握ります。中でも床材と壁材の選び方は、日常のストレスやトラブルを防ぐ重要な要素です。
床材については、滑りにくく、適度なクッション性のある素材を選ぶのが基本です。従来のフローリングは掃除のしやすさが魅力ですが、犬や猫の足腰には負担がかかるため、滑り止め加工のある床材や、コルク、クッションフロアがおすすめです。とくにシニア期のペットには、段差のないフラットな構造と併せて、足に優しい素材が欠かせません。
壁材については、爪による傷やにおい、汚れへの耐性が求められます。一般的なビニールクロスよりも、ペット対応の強化壁紙や、耐水性に優れたタイル壁、汚れを拭き取りやすい珪藻土などが適しています。さらに消臭・抗菌効果のある素材を選ぶと、清潔で心地よい空間づくりが可能です。
住まいは毎日使うものだからこそ、細かな素材の選択が、暮らしやすさを大きく左右します。ペットと人、双方にやさしい素材を選ぶことが、長く快適に暮らせる家づくりの第一歩です。
ペット臭対策に効果的な換気・空調設備とは
ペットとの生活で気になるのが「におい」の問題です。どれだけ清潔に保っていても、ペット特有の体臭や排泄臭、食べ物のにおいなどが蓄積されると、住まい全体の快適性が損なわれます。そこで重要となるのが、換気や空調設備の設計です。
まず、基本となるのが24時間換気システムの導入です。これは現代の住宅において標準化されつつありますが、特にペットのいる家庭では、換気効率の高いシステムを選ぶことが重要です。脱臭機能が強化された換気扇や、空気清浄機能付きのエアコンを取り入れることで、においを効率的に軽減できます。
さらに、トイレ周辺やペットの食事スペースには、局所換気扇を設置するのが効果的です。特にトイレの近くはにおいがこもりやすく、定期的な換気だけでなく、常時微弱な排気を行うことで、室内ににおいが広がるのを防ぎます。
空調設備もポイントです。ペットは人よりも体温調節が苦手なため、夏の暑さや冬の寒さに配慮した室温管理が欠かせません。温度ムラを減らすサーキュレーターの併用や、床暖房の導入も快適性を高める要素となります。
におい対策は日々の生活の満足度を大きく左右する要素です。換気と空調の両面から、快適な空気環境を整える工夫をしておきましょう。
安全性を高める電源・コード・家具の工夫
家づくりにおいて、見落とされがちなのが「家電と家具の安全性」です。ペットがいる家庭では、コンセントやコードの配置、家具の固定など、事故防止の観点から細やかな対策が必要となります。
まず、電源コンセントの位置は床から30cm以上の高さに設置すると、犬や猫が舐めたり噛んだりするリスクを減らせます。また、使わないコンセントにはキャップを装着し、誤って感電するのを防ぎましょう。特に子犬や子猫の時期には、好奇心からコードをかじることがあるため、モールで隠す、家具裏に配線するなどの工夫が欠かせません。
コード類については、家電の数が多いリビングやキッチン周辺で特に注意が必要です。足に絡まったり、引っ張って家具や家電が倒れるなどの事故を防ぐため、コードボックスやカバーを活用し、整理整頓を徹底しましょう。
家具についても、転倒や落下を防ぐための配慮が求められます。キャットタワーや本棚などの縦型家具は、壁面に固定することが基本です。また、軽量なインテリアはペットが飛び乗ると動いてしまう可能性があるため、滑り止めマットを敷いて安定させると安心です。
こうした細かな工夫の積み重ねが、ペットの安全性を高め、住まい全体の安心感にもつながります。

外構・庭・玄関まわりのペット仕様ポイント
脱走防止フェンスと庭のデザイン最適解
庭や外構部分はペットにとって自由に動ける貴重な空間ですが、一歩間違えると「脱走リスク」を伴う危険な場所にもなり得ます。そこで、脱走を防ぎながらも快適に過ごせる外構設計が求められます。
まず重要なのがフェンスの高さと構造です。小型犬でもジャンプ力は高く、1.2メートル以上の高さが推奨されます。中型犬以上では1.5メートル以上が理想です。加えて、フェンスの下部に隙間があると、掘って逃げ出すこともあるため、コンクリートやブロックでしっかり塞ぐことが大切です。
猫の場合は、登る・飛び移るという特性を持つため、フェンスの内側にネットを張る、上部を内側に折り曲げるなどの工夫が有効です。視覚的なバリアとして植栽を使う方法もありますが、誤って食べると中毒を起こす植物には十分注意しましょう。
庭の素材にも配慮が必要です。人工芝やゴムチップなど、足を傷めにくい柔らかい素材を使うと、ペットに優しい空間になります。夏場の地熱にも注意が必要で、日よけの設置や、タープの活用などで熱中症対策を講じましょう。
安全と自由を両立させた庭づくりは、ペットにとって最高の遊び場になります。
玄関・勝手口・駐車場との関係性をどう考える?
家の外と中をつなぐ「出入口」は、ペットの安全と暮らしやすさにおいて非常に重要なポイントです。とくに玄関、勝手口、駐車スペースの設計は、ペットとの生活動線に大きな影響を与えます。
玄関は来客時にペットが飛び出してしまうリスクがあるため、内扉を設けた二重構造や、ペットゲートの設置が有効です。また、玄関横に足洗い場を設けておけば、散歩後の手入れもスムーズになり、室内の清潔も保たれます。
勝手口は家事動線の一部として便利ですが、外からの侵入リスクにも注意が必要です。外に出てしまったペットが勝手口付近に留まり、事故につながる可能性もあるため、屋外にはフェンスや柵を設けると安心です。
駐車場はクルマの出入りが多いため、ペットの飛び出し防止策を徹底しましょう。シャッターや門扉を備えたクローズドタイプのカーポートや、タイヤにペットが巻き込まれないような動線計画も必要です。
出入口は毎日の出入りが発生する重要な場所です。安全性と機能性を備えた設計により、ペットとの生活がよりスムーズで快適になります。
ペットと暮らす家の立地と周辺環境
ペットとの外出に適したエリア選びとは
家づくりにおいて、建物そのものの設計や設備はもちろん大切ですが、「どこに住むか」という立地条件も、ペットとの暮らしに大きな影響を与えます。特に犬との暮らしでは、日々の散歩環境が心身の健康に直結します。
まず確認したいのは、徒歩圏内に散歩しやすい公園や緑地があるかどうかです。アスファルトばかりの道では、夏場は肉球を火傷しやすく、ストレスも溜まりがちです。緑が多く、歩道が整備されたコースが近くにあると理想的です。また、犬の散歩を歓迎している地域であれば、他の飼い主とも自然とコミュニケーションが生まれ、社会性も育まれます。
猫の場合でも、静かな環境かつ車通りの少ない立地は安心感につながります。窓辺から外を眺めるのが好きな猫にとっては、近くに自然が感じられる景色があるだけでもリラックスできるでしょう。
また、日中の騒音や人通りが多すぎるエリアは、敏感なペットにとってストレス源となるため、静かな住宅街や自然に近い場所を選ぶのが安心です。
ペットと一緒に暮らす上で、「どんな環境で過ごすか」も家選びの重要な視点です。散歩、遊び、リラックスできる空気感まで含めて、立地の良し悪しを見極めていきましょう。
動物病院・トリミングサロン・公園との距離
ペットと暮らす家庭にとって、住宅の周辺に「ペット関連の施設」が充実しているかどうかは、日常の安心度を左右します。特に動物病院とトリミングサロン、公園の距離は、家を選ぶうえでの大きな判断材料となります。
まず動物病院については、車で10分以内、できれば徒歩や自転車圏内に1軒あると非常に心強いです。急な体調不良やケガにすぐ対応できるかどうかは、ペットとの暮らしの質を高めるポイントになります。さらに、予防接種や定期検診も含めて、通いやすさは大切な判断軸です。
トリミングサロンやペットショップも、定期的な利用があるなら近くにあると便利です。特に大型犬の場合、送迎サービスを利用できるかどうかもチェックしておくとよいでしょう。また、預かり対応の有無も、出張や旅行時の預け先選びに役立ちます。
公園に関しては、犬の散歩はもちろん、ちょっとしたリフレッシュにもつながります。ドッグランが併設されているか、ペット可の芝生スペースがあるかなど、利用のしやすさを事前に調べておくと安心です。
地図で距離を見るだけでなく、実際に現地を歩いて確認し、ペット目線で「使いやすいか」「安全か」を判断することが大切です。

ペットと暮らす家づくりで失敗しない資金計画と制度活用
ペット共生住宅はローン審査に影響する?
ペットと暮らす家を建てる際、「住宅ローンに影響するのでは?」と心配される方も少なくありません。結論からいえば、ペット共生住宅であることがローン審査に直接マイナスに働くことはありません。ただし、プランによっては追加コストが発生するため、しっかりとした資金計画が求められます。
たとえば、防音対策や滑りにくい床材の採用、ペットゲートや専用の設備を設けるなどは、一般的な建築費用よりも高額になることがあります。この際、住宅ローンの借入限度額や返済年数とのバランスを取りながら、全体予算の中でうまく組み込む工夫が必要です。
また、住宅金融支援機構の「フラット35」など、省エネ性や耐久性に優れた住宅には金利優遇が適用されるケースもあります。たとえばペット対応の高性能設備が、省エネや健康増進に貢献する仕様であれば、間接的に評価対象となることもあります。
金融機関によって審査基準が異なるため、事前に相談しながら、必要書類や工事内容を整理しておくとスムーズです。ローンそのものに加え、設計・建築の進め方との連携も意識することで、無理のない資金計画を実現できます。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。
ペット仕様の住宅と補助金・税制の関係
現在のところ、日本において「ペット共生住宅」単独で受けられる補助金は少ないのが現状です。しかし、間接的に使える補助制度や税制優遇は存在し、それらを活用することでコストを抑えることが可能です。
代表的なのは、「長期優良住宅」や「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」といった環境性能の高い住宅に対する補助金です。滑りにくい床や換気性能の高い設備、太陽光発電など、ペットにも優しい仕様が結果的に補助対象となるケースもあります。
また、バリアフリー改修に関連した助成金や減税措置も見逃せません。高齢ペットやシニア世帯との共生を想定したフラット設計や手すり設置が、介護リフォームの対象となり、工事費の一部が補助されることもあります。
税制面では、住宅ローン減税や固定資産税の減免措置があるため、早めに市区町村の窓口や建築士と相談しておくとよいでしょう。
補助金制度は自治体ごとに異なるため、「ペットにもやさしい仕様」をキーワードにしながら、該当する制度を探し、賢く利用することが家計にも優しい家づくりにつながります。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。

実例で学ぶ!ペットと暮らす家の成功事例
ペットと家族の関係が変わった家とは?
実際にペットと共に暮らす家を建てた方々からは、「家を建ててから、ペットとの距離がさらに近くなった」という声が数多く寄せられます。家づくりの過程でペットの存在を意識し、空間設計に組み込むことで、物理的にも心理的にも家族の一員としての位置づけが明確になるのです。
たとえば、小型犬を飼っているご家庭では、階段の段差を緩やかにしたことで、シニア期でも元気に家の中を移動できるようになりました。毎日一緒にソファで過ごす時間が増え、「まるで会話ができるようになった」と表現する方もいます。
また、猫との暮らしでは、キャットウォークを造作したリビング空間が、猫と人の共通の遊び場に。家族みんなが天井を見上げながら話す機会が増え、自然とコミュニケーションが活発になったというエピソードも印象的です。
さらに、ペット専用の足洗い場を設けたことで、散歩後のケアがスムーズになり、衛生管理へのストレスが激減したという実感も多く聞かれます。小さな工夫が日々の安心に直結していることを物語っています。
ペットとの暮らしを家づくりに取り入れることで、ただの「飼い主とペット」ではない、共に生活をつくる“パートナー”としての関係が育まれていくのです。
トラブルを防いだ設計と実践アイデア集
ペットと暮らす中で起こりがちなトラブルも、事前の設計と設備選びで多くが予防できます。ここでは実際の経験を元に「防げたトラブル」と「それに対する対策」をご紹介します。
まず多いのが、ペットの脱走・迷子です。とあるご家庭では、勝手口の小さな隙間から犬が飛び出してしまったという経験がありました。そこで玄関や勝手口に二重扉を設け、さらに外構で囲うことで再発防止に成功しました。後からのリフォームではなく、新築時から取り入れることでコストも抑えられます。
また、コンセントやコードをかじられるという事例では、壁内配線とモール設置で事故防止につながりました。見た目にもすっきりし、掃除のしやすさも向上するという副次効果があったそうです。
猫の爪とぎによる壁紙の剥がれについては、傷に強い壁材に最初から変更。さらに爪とぎスペースを意図的に設けたことで、被害もぐっと減りました。猫自身も「ここでなら自由にできる」と安心して使っているそうです。
こうした経験からわかるのは、ペットの“困った行動”には必ず“理由”があり、設計の工夫でそれを解消できるということです。生活者の声を反映したアイデアは、誰にとっても役立つヒントになります。
元トップセールスが語る「ペットと暮らす家づくり」の盲点
実務で見た「後悔する家・喜ばれる家」の違い
これまで数百組以上の家づくりを支援してきた経験から言えるのは、「後悔する家」と「満足する家」は紙一重だということです。特にペットと暮らす家では、その差が設計初期の“意識の違い”に現れます。
後悔するパターンの多くは、「住んでから気づく」ことが発端です。滑る床材、騒音への無対策、におい対策の不足、トイレの配置ミス、階段の急勾配など、いずれも暮らし始めてからストレスとして浮き彫りになります。中には「リフォームで修正したが、最初からやっておけばよかった」と振り返る方も。
一方、喜ばれる家の共通点は、「ペットを“家族”として考えていた」ことです。動線・安全性・居場所を生活の一部として織り込み、日常がスムーズになるよう計画されています。そうした家では、ペットだけでなく家族全員が自然と笑顔になっていくのです。
プロの視点から見れば、ペットの特性や飼育環境を読み取った「提案力」が何より重要です。知識だけでなく、経験に基づいたヒアリングと提案が、家族に寄り添う家を形にします。
「家は暮らしの器」であり、「ペットと暮らす家は、心の器」でもある——その視点を忘れないことが成功のカギになります。
住宅会社に伝えるべきこと、聞くべきこと
理想のペット共生住宅を実現するためには、設計者や住宅会社との「認識の共有」が欠かせません。実はこのコミュニケーションの質が、仕上がりを大きく左右します。
まず大切なのは、「ペットの性格・年齢・飼育スタイル」を具体的に伝えることです。「小型犬1匹」ではなく、「12歳で足腰が弱ってきたチワワ」「日中は室内フリーで過ごす」など、具体的な情報が設計者にとって有効な判断材料になります。
また、「ペットがどの部屋でどう過ごすか」「どんなときに不安がるか」なども伝えておくと、より精度の高いプランが期待できます。逆に、設計者からは「換気計画」「音対策」「床素材」など、ペットの安全や快適性に関わる要素を確認してもらいましょう。
さらに、完成後の暮らしを見越して「掃除・メンテナンス性」についても、事前にチェックしておくことが後悔を防ぐポイントです。
「人の生活」と「ペットの生活」をどちらも見渡すことができる会社と出会うことが、真に満足できる家づくりのスタートラインになります。

まとめ|ペットと一緒に幸せに暮らす家づくりのヒント
家づくりを始めると、気になることが次々と出てきます。
ネットで情報を調べても、「これって本当に正しいの?」「うちに合ってるのかな?」と、かえって不安になる方も少なくありません。
そんな悩みに寄り添うために、私たちはNo.1住宅プランナーと、家づくりを経験した先輩ママたちと一緒に、“日本一信頼できる家づくりプラットフォーム”をつくりました。
▼後悔のない家づくりのために、まずは気になることから、ゆっくり見てみませんか?