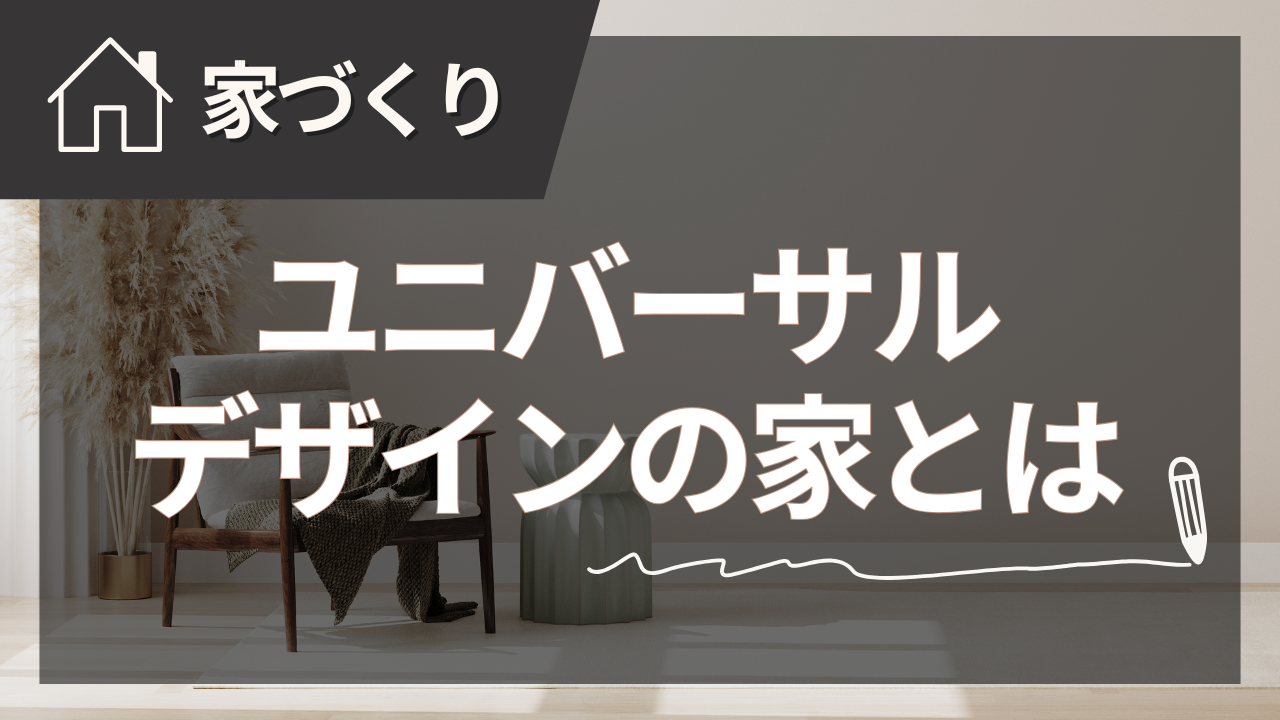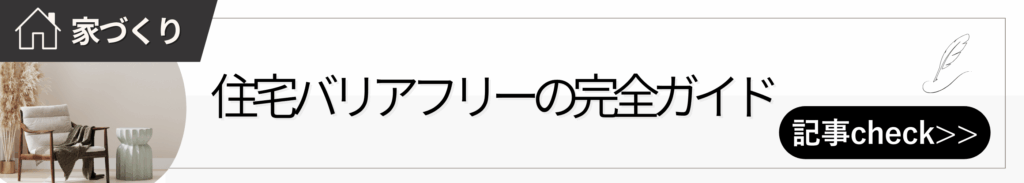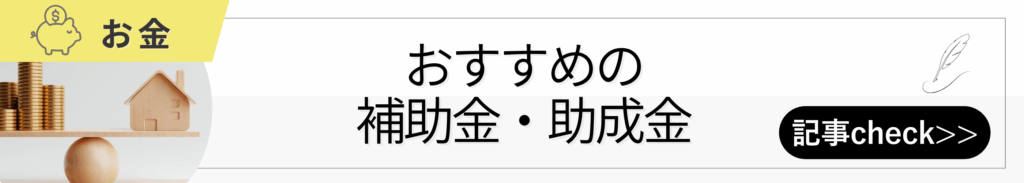そもそも「ユニバーサルデザインの家」とは何か?
ユニバーサルデザインの定義とバリアフリーとの違いをプロが解説
ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、すべての人が公平に使えるよう配慮された設計思想です。住宅においても、この概念は広く採用されつつあり、高齢者だけでなく、子育て世帯や共働き世帯、さらには未来のライフステージに備えた設計として注目されています。一方で、混同されがちな言葉に「バリアフリー」があります。バリアフリーは主に既存の障壁を除去するアプローチです。例えば段差の解消や手すりの設置など、具体的な物理的対策が中心です。それに対し、ユニバーサルデザインはそもそも障壁を生まない設計を目指します。つまり、バリアフリーは「対処療法」、ユニバーサルデザインは「予防医療」のような関係性です。これからの家づくりにおいて、誰もが長く快適に暮らせる環境を目指すなら、ユニバーサルデザインという視点は欠かせません。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。
なぜ今「ユニバーサルデザインの家」が注目されているのか?
現在、日本では高齢化と同時に、共働き世帯や単身世帯の増加、さらには多様性を重視する価値観の広がりなど、住まいに求められる役割が複雑化しています。そうした中で、特定の属性に限定されない「誰にとっても使いやすい家」が求められるようになってきました。また、2024年に施行された住宅設計ガイドライン改定では、居住者の多様性への配慮が明記され、行政や自治体がユニバーサルデザインの普及を後押しする動きも活発化しています。補助金の対象となるケースもあるため、経済的なメリットも無視できません。さらに、テクノロジーの進化により、ユニバーサルデザインの実現コストも下がってきており、以前に比べて導入のハードルが低くなっています。こうした時代背景も、今ユニバーサルデザインの家が選ばれる理由となっています。
住宅業界が考える、これからの「暮らしの標準装備」
かつては高齢者住宅や介護リフォームの文脈で語られることが多かったユニバーサルデザインですが、今ではハウスメーカー各社が「標準仕様」の中にその考え方を取り入れ始めています。たとえば、玄関の段差をゼロにする、すべてのドアを引き戸にする、廊下やトイレを広く確保するなど、従来ならオプション扱いだった仕様が、今や当たり前になりつつあります。さらに、「住み継がれる家」をキーワードに、子育て期からシニア期まで長期にわたって対応できる住宅設計が評価され、資産価値の観点からも注目されています。ユニバーサルデザインの家は、もはや特別な選択肢ではなく、これからの家づくりのスタンダードとして定着しつつあるのです。
まずは「どんな暮らしをしたいか?」を起点に、未来の家づくりの基準を考えてみましょう。

ユニバーサルデザインの家の特徴と7つの原則
「誰でも使いやすい」を実現する設計の基本とは?
ユニバーサルデザインの家づくりにおける最大の目的は、「使いやすさの最大公約数」を実現することです。つまり、特定の誰かに合わせた設計ではなく、老若男女すべての人が同じ空間で快適に過ごせるような配慮が必要です。その基本となるのは、身体的な負担を減らす動線設計や、感覚的に操作できる設備、移動しやすい広さや配置です。例えば、ドアノブを握りやすいレバー式に変更するだけでも、子どもや高齢者、手の不自由な人にとって大きな違いになります。また、視認性や触覚、音声案内など、五感への配慮も大切な設計要素です。これらは「目が悪くなったら」「足腰が弱ったら」ではなく、最初からそうならない前提で考えるべき時代になっています。
住宅に落とし込まれたユニバーサルデザインの7原則とは?
ユニバーサルデザインには、世界的に定義された「7つの原則」があります。
- 誰もが公平に使える
- 使う際の柔軟性がある
- シンプルで直感的に操作できる
- 情報がすぐに理解できる
- ミスや危険を最小限に抑える設計
- 身体的な負担が少ない
- 利用しやすい寸法と空間の確保
住宅にこの原則を落とし込むと、具体的には段差をなくす、手すりを設置する、廊下の幅を広くする、視覚だけでなく音声でも情報が伝わるようにするなどが該当します。また、照明やスイッチ、コンセントの位置を工夫することで、どの世代の方でもスムーズに生活できる環境を整えることが可能になります。こうした配慮が、家族構成やライフステージが変わっても「ずっと使いやすい家」を実現してくれます。
実際の住まいに導入される具体的なアイデアと技術
例えば、玄関をフラットにすることで、ベビーカーでも車椅子でもスムーズに出入りできます。トイレや浴室の扉を引き戸にするだけでも、使いやすさが格段に向上します。さらに、最近ではスマートホーム技術との連携により、声やタッチパネルで家電を操作できる仕組みも注目されています。これにより、動きに制限のある方でもストレスなく生活が可能になります。また、外壁や内装の素材選びでも、滑りにくく衝撃を吸収する床材、視認性の高い色分けなど、工夫の余地は無限にあります。こうした技術の積み重ねが、日常の安心と快適さを支えているのです。
住まいに取り入れる工夫は、住宅展示場などで実物を見るとイメージしやすくなります。

ユニバーサルデザインの家のメリットと後悔しない判断ポイント
家族全員が安心して暮らせるという最大の安心感
ユニバーサルデザインの家の最大のメリットは、「誰にとっても暮らしやすい」という点にあります。家族の中には、小さな子どもや高齢者、身体の状態に応じて動きづらい方もいるかもしれません。それぞれが違う状態でも、同じ空間で快適に過ごせるように設計されているのがこの住宅の強みです。たとえば、段差のない玄関やトイレは、転倒リスクを減らし、家族全員の安全を確保します。広めの通路やドア幅は、ベビーカーや車椅子の移動もスムーズにし、子育てや介護のしやすさにも直結します。特定の誰かに合わせた家ではなく、全員にとって優しい設計であること。それが結果的に、家族の絆を深め、毎日のストレスを減らすことにつながります。
10年後・20年後も快適に暮らせる「未来対応」の間取り
「今は健康だから大丈夫」と思っていても、年齢とともに体力や感覚は変化していきます。ユニバーサルデザインの家は、そうした未来の変化に柔軟に対応できる設計思想がベースになっています。たとえば、後から手すりを追加できる下地の準備、廊下やドアをあらかじめ広めに設計するなど、初期段階で少しの工夫をするだけで、将来的なリフォーム費用を抑えることができます。また、子どもが成長して独立した後の空間活用や、在宅勤務や趣味の部屋への転用など、ライフステージの変化に合わせて暮らし方を変化させやすいのも特徴です。短期的な視点ではなく、20年・30年先の「未来の自分たち」にとっても使いやすいかどうかを想像してみることが大切です。
デメリットも事前に知る:コスト・スペース・掃除の観点から
ユニバーサルデザインの家にも、知っておくべきデメリットは存在します。代表的なものは「コスト」「スペース」「メンテナンス性」です。まずコスト面では、スロープや広めの空間設計、スマート設備などの導入で建築費が一般的な住宅より高くなる傾向があります。しかし、これは長い目で見れば、将来の改修費や医療費、介護負担を抑える投資ともいえます。また、スペースが広くなる分、建坪が限られる都市部では、ほかの部屋がやや狭くなるケースもあります。優先順位を見極め、生活動線をしっかり整理することで解決できます。掃除や換気についても、段差がない構造ゆえにホコリがたまりやすい面がありますが、24時間換気や空気清浄機の導入、掃除ロボットの活用で十分に対応可能です。
デメリットを正しく理解し、先回りして対策を講じることが、後悔しない家づくりへの第一歩です。

ユニバーサルデザインの家はどんな人におすすめ?
子育て世代が「今」取り入れるべき理由とは?
「ユニバーサルデザイン=高齢者向け」と思われがちですが、実は子育て世代にも大きなメリットがあります。段差のない床はつまずきや転倒のリスクを減らし、ベビーカーのまま室内に入れる間取りは、外出や帰宅がスムーズになります。また、リビングやキッチンから子どもを見渡せる空間設計や、引き戸の採用で指を挟むリスクを軽減するなど、安全面にも細やかな配慮が施されています。さらに、トイレやお風呂の広さ、手すりの設置が、小さなお子さんのトレーニングやお風呂のお世話を助けてくれるなど、子育て中のストレスを軽減する効果もあります。子どもが成長してからも快適に使えることを考えると、子育て期にユニバーサルデザインを取り入れる価値は非常に高いといえるでしょう。
将来の介護リスクに備えるなら今が建て時?
高齢化社会が進む中、自宅での介護やケアの可能性が高まっています。突然の病気やケガで、急に生活環境を見直さなければならないケースも少なくありません。ユニバーサルデザインの家は、そうした「まさか」に備える保険のようなものです。車いす対応のトイレやスロープのある玄関、手すりの設置を見越した設計がされていれば、介護が必要になったときにも慌てることなく対応できます。また、介護保険制度における住宅改修の補助金を活用することで、費用の負担を抑えながら必要な設備を整えることも可能です。
「まだ早い」と感じるかもしれませんが、余裕のある今だからこそ、将来の安心を設計に組み込むことが重要です。
共働き・単身世帯にも便利なユニバーサル住宅の隠れた利点
共働き世帯や単身世帯にとっても、ユニバーサルデザインの家は非常に合理的な選択肢です。例えば、荷物を持ちながらも簡単に開けられるドア、スマートロックや音声操作が可能な家電の導入など、利便性と効率性に優れています。また、掃除がしやすく、動線がシンプルな設計は、忙しい毎日においてもストレスを感じさせない工夫といえます。さらに、ライフスタイルが変わっても柔軟に対応できる可変性のある間取りは、将来的な賃貸や売却時の資産価値にも好影響を与えます。合理性を重視する世帯こそ、無駄を省きながらも快適な暮らしを実現できるユニバーサルデザインの恩恵を享受できるのです。

ユニバーサルデザインの家を実現する間取りと施工の工夫
玄関・廊下・階段に仕込まれた安心と便利のテクニック
ユニバーサルデザインの家において、玄関と廊下、階段の設計は安全性と快適性を両立する重要なポイントです。まず玄関は、段差をなくすことで転倒リスクを大幅に軽減できます。スロープと階段を併設することで、ベビーカーや車椅子の出入りもスムーズです。玄関内にベンチを設けることで、靴の脱ぎ履きが楽になり、高齢者や妊婦にとっても負担が減ります。廊下については、車椅子の回転が可能な90cm以上の幅を確保することで、将来的な介護にも備えられます。また、手すりの取り付けを前提とした構造にしておくことで、必要になった時の改修費用も抑えられます。階段では、緩やかな勾配や滑りにくい素材の使用、夜間でも足元が見やすいLED照明の設置など、安全性に直結する設計が重要です。
細部にこそ、暮らしの快適さを支える本質が宿るのです。
トイレ・浴室・キッチンで見直したい、ユニバーサルデザインのポイントとは?
トイレや浴室、キッチンなどの水回りは、日常生活の中でも使用頻度が高く、年齢や身体状況によって使い勝手が大きく左右される空間です。だからこそ、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた設計が重要になります。トイレでは、入り口の段差をなくすことが基本です。便器周辺に手すりを設置する、広めのスペースを確保するなど、将来的に介助が必要になった際の対応も見越した設計が理想的です。さらに、寝室の近くに配置すれば、夜間の移動距離が短くなり、転倒リスクや冬場のヒートショックも軽減できます。浴室については、滑りにくい床材の使用や、またぎやすい高さの浴槽、手すりの設置が基本です。洗い場にゆとりを持たせることで、介助者や親子での入浴も楽に行えるようになります。段差のないフラットな出入口も忘れてはいけません。キッチンでは、調理台の高さを調節できる仕様にすることで、車椅子使用者や小柄な方でも快適に使えます。また、引き出し式の収納や、音声やタッチで操作できるIHやレンジフードなどの最新設備を取り入れることで、家事負担を減らすことが可能です。
暮らしの中心となる水回りにこそ、ユニバーサルデザインの真価が問われるのです。

リフォームでユニバーサルデザインを導入するコツ
新築だけでなく、既存住宅にユニバーサルデザインを導入する「リフォーム」も有効な手段です。特に築年数の経った家では、段差や狭い通路、古い設備が生活の不便や危険につながっているケースもあります。リフォームでは、まず「どこに不便を感じているか」「将来的に何が必要になるか」を家族で話し合うことが大切です。次に、その課題を解決できる部分から優先して改修することで、費用と効果のバランスを最適化できます。たとえば、玄関にスロープを設置する、浴室の入口をフラットに変更する、トイレのドアを引き戸にするなど、比較的コストを抑えながら効果が高い部分から取り組むのがポイントです。また、補助金や助成制度を活用することも視野に入れておきましょう。介護保険制度や各自治体のリフォーム補助を利用することで、自己負担を軽減できます。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。
「今の家をより快適に、より安全に」。その思いに応えてくれるのが、ユニバーサルデザインリフォームの価値です。
ユニバーサルデザインの家を建てるならどこに相談すべき?
ハウスメーカー選びで見るべき「対応力」と「設計力」
ユニバーサルデザインの家づくりにおいて、ハウスメーカーや工務店の選定は成功の鍵を握る重要なポイントです。単に「段差がない家ができます」といった表面的な対応ではなく、「家族構成」「将来の変化」「暮らし方の多様性」まで理解し、設計に落とし込める力があるかが重要です。そのためには、まずその会社がどれだけユニバーサルデザインの実績を持っているかを確認しましょう。施工事例や、提案力、柔軟な設計変更に対応できるかなど、カタログやHPだけではわからない部分も多いので、できるだけ直接話を聞くことが望ましいです。また、建築士やコーディネーターにユニバーサルデザインの理解があるかどうかもチェックポイント。設計段階での丁寧なヒアリングや、生活動線を重視した提案ができるかが、真の「対応力」です。
住宅展示場や相談会などを活用して、しっかりと見極めていきましょう。
住宅展示場・モデルハウスを活用した情報収集術
ユニバーサルデザインの家を検討しているなら、住宅展示場やモデルハウスの見学は非常に効果的です。実際の空間を体感することで、パンフレットやネットでは得られない「リアルな暮らしのイメージ」を掴むことができます。特に注目すべきは、玄関からリビング、トイレ、浴室などの動線や広さです。車椅子やベビーカーの動きを想定しながら歩いてみると、自分たちの生活にどうフィットするかが具体的にわかってきます。また、見学の際は「生活動線をどんな人がどう使うか」という視点で観察するのがポイントです。子育て中のママや高齢者、共働き世帯など、モデルケースをイメージして見ることで、細かな設計の工夫に気づくことができます。見学後は、気になる点をまとめてスタッフに質問することで、理解が一層深まります。
信頼できる建築士やコーディネーターと出会うために
ユニバーサルデザインの家づくりでは、設計段階からの「伴走」がとても大切です。そのためには、ただの「設計者」ではなく、自分たちのライフスタイルや未来を見据えて提案してくれる「パートナー」と出会う必要があります。建築士やコーディネーターを選ぶ際には、過去の実績や専門性、提案力を見ると同時に、「話しやすさ」「信頼感」も非常に重要です。家族構成や将来設計を踏まえて、親身に相談に乗ってくれるかが、理想の住まいづくりの決め手になります。また、初回相談でのヒアリング内容や、課題に対する解決策の提示力も、判断材料になります。迷ったときは、複数人と話して比較するのもひとつの手です。
良いパートナーと出会えれば、家づくりの不安も楽しみに変わっていきます。

体験談でわかるユニバーサルデザイン住宅のリアル
子育てママが語る「段差ゼロのありがたみ」
Aさん(30代・2児の母)は、玄関や浴室の段差を一切なくしたユニバーサルデザインの家を選びました。「毎日の外出でベビーカーを持ち上げる手間がなくなって、本当にラクになりました」と笑顔で語ります。特に便利だと感じたのは、玄関に設けた腰かけベンチ。「子どもに靴を履かせるとき、自分も安定して座れるのでケガの心配が減りました」とのこと。また、掃除がしやすい設計になっているため、子育ての合間でも短時間で家中を整えられるという点でもメリットを実感しているようです。
ユニバーサルデザインの家に住んで感じたリアルな声
70代夫婦が選んだ「将来に備える家づくり」の本音
Bさんご夫妻は、退職を機にバリアフリーからさらに一歩進んだ「ユニバーサルデザインの家」への建て替えを決意しました。「まだ健康だけど、先のことを考えて設計しておくのが安心」と話すご主人の言葉どおり、玄関・トイレ・浴室すべてが段差なしで、将来車椅子になっても対応できる設計に。奥様は「台所の高さが少し低く調整されていて、足腰に負担がかからない。毎日の料理が楽しくなりました」と語ります。日々の動作を快適にする工夫が積み重ねられた家は、暮らしの質を大きく変えたようです。医療や介護の現場で働いていたご主人の視点からも、「予防としての住まいづくり」はもっと広まってほしいと強く実感されているとのことでした。
共働き世帯が語る「時短と快適性を両立できた家」
Cさん夫妻は共働きの30代。子育てと仕事に追われる毎日を支える家として、ユニバーサルデザインを採用しました。「忙しいからこそ、動線のムダを省いた家で過ごしたいと思った」とご主人。特に評価が高かったのは、回遊できる動線と自動化された設備。「料理中に声で換気扇や照明が操作できるのは地味に便利です」と奥様。また、浴室やトイレの清掃もルンバや自動洗浄機と相性がよく、「何より、時間を家族との会話に使えるようになったのが一番のメリットかもしれません」と話してくれました。
今やユニバーサルデザインは、介護や高齢者のためだけでなく、誰にとっても“暮らしやすさ”を追求できる選択肢となっているのです。
ユニバーサルデザインの家とは、すべての人に優しい未来基準の住まい
ユニバーサルデザインの家とは、年齢や性別、身体状況にかかわらず、すべての人が安全で快適に暮らせるよう設計された住まいのことです。段差のない床、広い廊下、視認性の高い色彩設計、音声や感覚に配慮した設備の導入など、その配慮は細部にまで及びます。
この家づくりの思想は、決して高齢者や障がい者のためだけではありません。子育て世帯、共働き家庭、単身者…どんなライフスタイルでも柔軟に対応できる“未来対応型”の設計です。コストやスペース、清掃などの面で課題はあるものの、それを補って余りある快適性と安全性が得られます。また、長期的な視点で見れば、リフォーム費や介護対応の負担も軽減でき、経済的にも合理的です。
新築はもちろん、リフォームでも導入できるユニバーサルデザインの家。この時代の新しい“標準仕様”として、これからの家づくりに取り入れてみてはいかがでしょうか?

まとめ|ユニバーサルデザインの家を建てるためのポイント
家づくりを始めると、気になることが次々と出てきます。
ネットで情報を調べても、「これって本当に正しいの?」「うちに合ってるのかな?」と、かえって不安になる方も少なくありません。
そんな悩みに寄り添うために、私たちはNo.1住宅プランナーと、家づくりを経験した先輩ママたちと一緒に、“日本一信頼できる家づくりプラットフォーム”をつくりました。
▼後悔のない家づくりのために、まずは気になることから、ゆっくり見てみませんか?