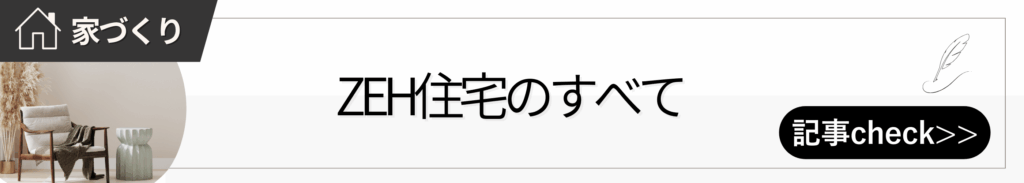HEAT20の基本を理解する
HEAT20とは何か?その定義と背景
HEAT20とは、「20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」が提唱する、高断熱住宅の新たな性能基準です。この団体は、住宅会社や建材メーカー、大学の研究者などで構成されており、従来のZEH基準を超える断熱水準を目指しています。HEAT20は「室温」「エネルギー削減」「外皮性能」という3つの観点から住宅の快適性と省エネ性を評価します。
背景としては、エネルギー価格の高騰や地球温暖化への対応があり、ただの“断熱”では不十分な時代になってきました。HEAT20の採用は、今後の家づくりにおける重要な判断基準となるでしょう。
HEAT20の概念を理解することは、これからの住宅性能選びにおいて欠かせません。
HEAT20とZEHの違いをわかりやすく比較
ZEH(ゼッチ)は「使うエネルギー ≦ 創るエネルギー」を目指した住宅で、省エネ・創エネを中心とした概念です。一方、HEAT20は断熱そのものの性能をさらに突き詰め、「いかに少ないエネルギーで快適な暮らしができるか」を追求した基準です。
ZEHが太陽光発電を含めて一次エネルギーの消費量を基準とするのに対し、HEAT20は建物の基本性能、特に外皮性能(UA値)にフォーカスしています。そのため、太陽光が難しい敷地でも、断熱・気密性を高めることでHEAT20のメリットを享受できます。
両者を組み合わせて設計することも可能であり、HEAT20+ZEHのような家は、快適性と省エネ性を兼ね備えた最先端住宅とも言えるでしょう。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。

HEAT20が注目される社会的背景
カーボンニュートラルとHEAT20の関係
2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、住宅業界も大きな変革を迫られています。その中核となるのが、HEAT20のような高断熱基準です。建築物から排出されるCO2を抑えるためには、エネルギー消費そのものを減らす設計が必要です。
HEAT20は、室内温度を一定に保ちやすい設計により、冷暖房の使用頻度を大幅に抑えられます。これはすなわち、家庭からのエネルギー消費の削減=CO2排出量の削減に直結するわけです。
住宅1棟あたりの省エネインパクトは大きく、HEAT20の普及は社会全体にとっても価値ある選択肢と言えます。
日本の断熱水準の現状と課題
日本の住宅の断熱水準は、欧米に比べて長らく遅れていました。断熱等級4(2025年から義務化)が長らく最高基準だった一方、HEAT20はその上をいく断熱等級5〜7をカバーします。
従来は「夏を涼しく」が中心だった日本の住宅設計ですが、近年は冬の快適性や健康維持にも注目が集まっています。特に高齢者や子育て世帯にとって、室温の安定性は非常に重要な指標です。
HEAT20はこうした社会的課題に応えるかたちで生まれた基準であり、今後の住宅性能の新たな“ものさし”になっていくでしょう。

HEAT20の導入メリットとは?
一年中快適に過ごせる室内環境
HEAT20の家は、外気温に左右されにくい快適な室内環境を実現できます。夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して温度差の少ない暮らしができるため、ストレスが大幅に減ります。
たとえば、G2グレードの住宅では、冬でも13℃以下になることはほとんどなく、暖房に頼らず快適に過ごせるレベルに設計されています。
室温の安定は睡眠の質や体調管理にも直結し、小さなお子様や高齢者がいる家庭にとってはとても重要な要素となります。
結露・カビ・シロアリを防ぐ構造の工夫
断熱性能が低い家では、壁内や窓周りに結露が生じやすく、そこからカビが発生し、シロアリやダニが繁殖する原因になります。これにより、健康被害や住宅の劣化が進むリスクがあります。
HEAT20基準を満たす住宅では、外皮性能の強化によって表面温度の変化が抑えられ、結露を防止できます。その結果、住宅の長寿命化にも貢献します。
家族の健康と建物の資産価値の両方を守れるという意味で、HEAT20は極めて合理的な選択肢です。
光熱費を大幅に削減できる理由
冷暖房にかかるエネルギーを最小限に抑えられるため、HEAT20の家は月々の光熱費が圧倒的に安くなります。特に電気代やガス代の高騰が続く今、家計負担を抑えるという観点からもHEAT20は魅力的です。
G2・G3グレードでは、平成28年基準比で暖房エネルギーを最大80%も削減可能とされています。初期投資が必要でも、長期的に見れば十分元が取れる設計です。
暮らしの快適さと経済性を両立できる、それがHEAT20の大きな魅力です。

HEAT20の注意点と導入の壁(地域区分/住宅メーカー)
初期コストとメンテナンス費用の現実
HEAT20を導入するためには、断熱材やサッシなどの建材を高品質なものにする必要があり、建築コストが上昇します。特にG3など上位グレードでは、数百万円単位での費用差が出ることもあります。
さらに、高性能な換気システムなどは、20年程度の耐用年数があり、定期的なメンテナンスや交換が必要になります。導入時だけでなく、ライフサイクルコストを含めて総合的に検討する必要があります。
コストに見合う価値があるかどうかは、ライフスタイルや優先順位に応じて判断することが重要です。
地域ごとの基準と住宅会社選びのポイント
HEAT20は全国一律の基準ではなく、地域区分によって必要なUA値やη値が異なります。そのため、自分の住むエリアに適した断熱設計ができる住宅会社を選ぶことが重要です。
施工実績や断熱性能の開示、第三者評価などを確認し、信頼できる会社を見極めましょう。また、説明の中でHEAT20の具体的なグレードについて明確に答えられる営業マンがいるかどうかも一つの指標です。
断熱は「見えない性能」だからこそ、施工の質と住宅会社の透明性が非常に大切になります。

具体的なHEAT20導入ステップ
HEAT20対応の住宅会社を選ぶ際のチェックポイント
まずは、HEAT20の基準に対応した施工実績のある住宅会社を選ぶことが第一歩です。カタログやHPにHEAT20の記載があるかどうか、またG1〜G3のどのグレードに対応可能かを確認しましょう。
さらに、断熱材や窓のスペック、設計段階での外皮計算の有無なども重要な判断基準です。打ち合わせ時には、施工例や数値的な根拠(UA値・η値など)を確認できるかチェックしましょう。
納得できるまで説明してくれるパートナー選びが、HEAT20導入成功の鍵となります。
断熱等級の違いによる住宅性能の変化
HEAT20のグレードごとに、断熱性能の水準は大きく異なります。G1は最低限の快適さを実現するレベル、G2は全館暖房をしなくても快適な居住空間、G3は高断熱高気密住宅の最上位レベルです。
特にG3レベルになると、室温の変動が非常に小さくなり、住宅全体が温度のバリアフリーになります。この違いは、実際に住んでみると体感温度や光熱費に大きく影響します。
快適さ・健康・家計へのインパクトを比較して、自分に合ったグレードを選ぶことが大切です。
HEAT20の施工事例とリフォーム活用
新築だけでなく、リフォームでもHEAT20基準に近づけることは可能です。例えば、内窓の設置、外壁・屋根の断熱材の追加、床断熱の強化などがあります。
実際にG2相当の性能を目指したリフォームでは、冬の室温が10℃以上改善したという事例もあります。また、結露や湿気の悩みが解消され、健康面でも大きな改善が見られるという声もあります。
長く住む家だからこそ、性能向上リフォームにもHEAT20の視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
どんな人にHEAT20はおすすめか?
子育て世代にとってのHEAT20の価値
小さなお子様がいるご家庭では、冬のヒートショックや夏の熱中症リスクが気になります。HEAT20は、家全体の温度差が小さいため、子ども部屋やトイレ、脱衣所まで温度が安定し、安全性が高まります。
また、結露やカビの抑制によって、アレルギー症状の軽減にもつながります。夜中の授乳やおむつ替えでも、暖房が切れて寒くなるようなこともありません。
子どもたちの健やかな成長と、家族全体の安心を考えるなら、HEAT20は非常に価値ある投資と言えるでしょう。
健康志向・環境配慮型の家づくりを目指す方へ
HEAT20の住宅は、健康への配慮と環境負荷の低減の両方を叶えられる設計です。特に健康寿命を延ばしたいシニア層や、エシカルな暮らしを意識する世代には高い親和性があります。
また、将来的なエネルギー政策の変化や補助金制度への対応も柔軟です。HEAT20に対応していると、自治体の補助金や認定制度を活用できる可能性も高くなります。
今だけでなく、10年後・20年後の暮らしを見据えたとき、HEAT20基準の家は「持続可能な暮らし」への一歩となります。

まとめ|HEAT20で叶える、未来志向の家づくりとは
家づくりを始めると、気になることが次々と出てきます。
ネットで情報を調べても、「これって本当に正しいの?」「うちに合ってるのかな?」と、かえって不安になる方も少なくありません。
そんな悩みに寄り添うために、私たちはNo.1住宅プランナーと、家づくりを経験した先輩ママたちと一緒に、“日本一信頼できる家づくりプラットフォーム”をつくりました。
▼後悔のない家づくりのために、まずは気になることから、ゆっくり見てみませんか?