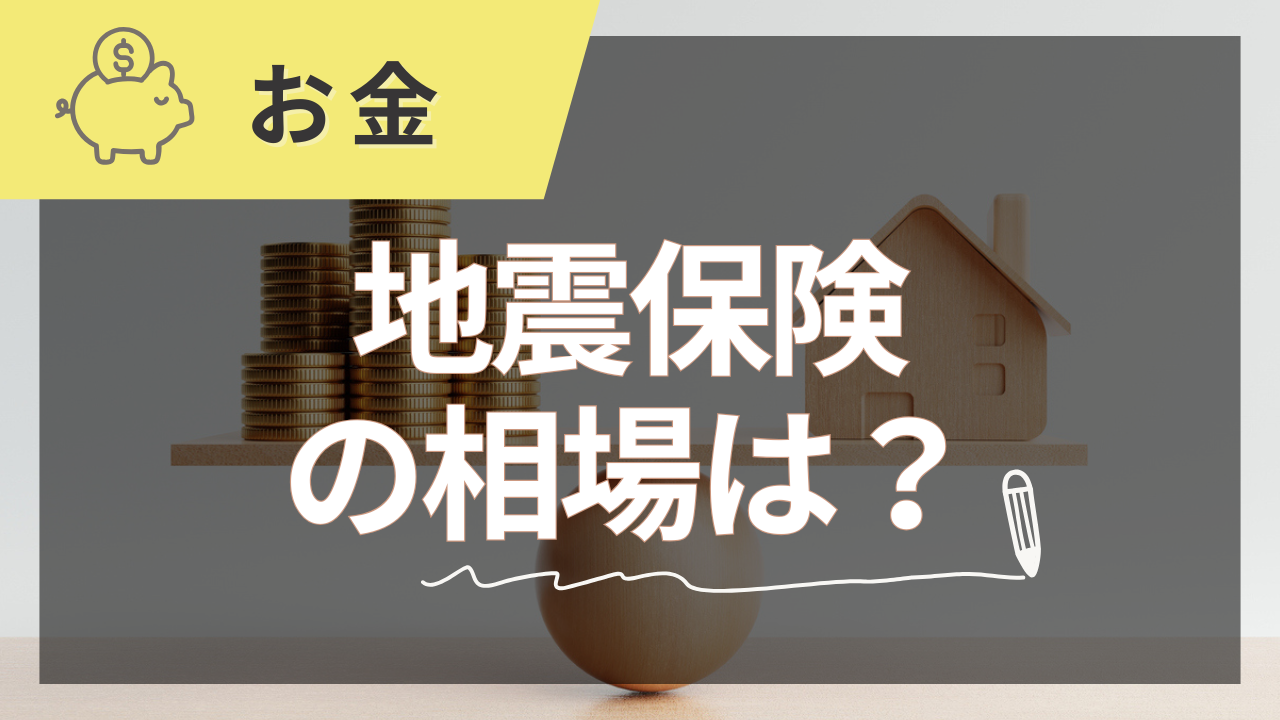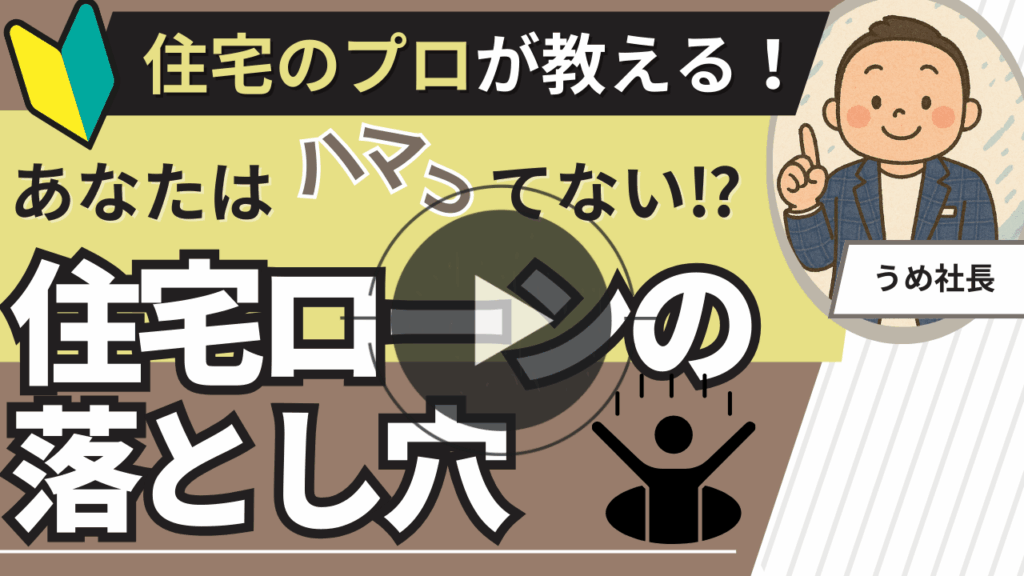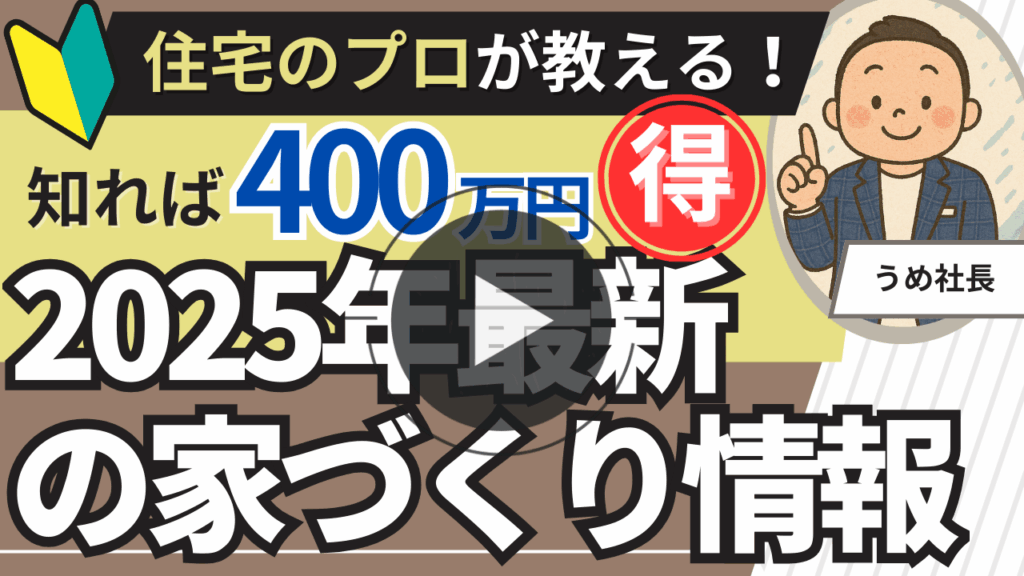Answer
地震保険の相場は「地域」「建物構造」「築年数」「保険金額」「免責金額」の5要素で大きく変動します。
2025年7月の先輩ママ5人座談会でも「思っていたより高かった」「建てる前に知っておきたかった」という声が多数。リスクを把握し、備えを最適化することがカギです。
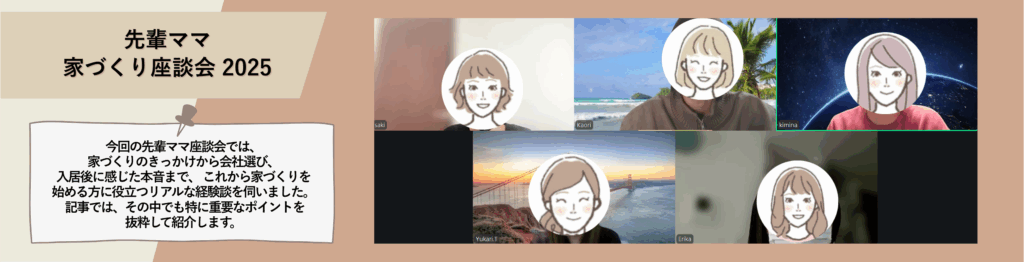
地震保険の保険料はどう決まるの?
Answer
保険料は「地域・構造・築年数・保険金額・免責金額」の5つの要素で決まります。
Why?
地震保険は国の制度に準じて料率が決められており、リスクが高いエリアほど保険料も高く設定されています。たとえば首都圏の木造住宅は、同じ条件の北海道内陸部の物件と比べて2倍近い保険料になることもあります。建物構造では、鉄筋コンクリート造のマンションは耐火性が高いため、木造よりも料率が下がります。また、築年数が古くなると時価評価が下がり保険料も変わる一方で、再建に必要な費用は下がらないというギャップも発生します。
先輩ママの事例
Aさん:「引っ越しを考えて地震保険を調べたら、同じ間取りでも地域で1万円以上差があると知って驚きました。土地の選び方まで変わりました」
Cさん:「築18年の木造住宅に住んでいますが、耐震診断をして補強したところ、保険料が思ったより安くなって助かりました」
補足Point
各保険会社の試算ツールを使えば、住所・建物構造・築年数を入力するだけでおおよその保険料が分かります。引っ越しやリフォームの際には、事前にシミュレーションする習慣をつけましょう。
保険金額と免責の設定でどれだけ相場が変わるの?
Answer
保険金額の上限設定や免責金額の有無で、年間1〜2万円以上の差が出ることもあります。
Why?
地震保険は火災保険の30〜50%までが上限で、設定額を上げるほど保険料も上がります。一方、自己負担である免責金額を設定すれば、保険料は下がりますが、小規模損害には補償が出ない可能性があります。たとえば5万円の免責を付けるだけで5〜8%保険料を削減できますが、実際に被害が起きた際に自己負担が大きくなる点には注意が必要です。
先輩ママの事例
Bさん:「免責を0円にして加入したら、少し高かったけど安心感が段違い。地震のときは即連絡してすぐ対応してもらえました」
補足Point
「最低限の生活再建資金+家財分」を目安に保険金額を設定し、免責はできるだけ0円に近づけるのが基本戦略です。
地域や建物構造別の相場はどう違うの?
Answer
同じ建物でも、地域や構造によって年間保険料が大きく異なります。
Why?
耐火構造のマンションであれば料率は低く抑えられますが、木造戸建ては非耐火扱いとなり、地震リスクが低くても料率が上がります。また、省令準耐火構造の認定を受けることで木造住宅でも大幅に保険料が下がるケースもあります。例えば、同じ築年数・面積でも東京と帯広では年間2万円以上の差がつくことも珍しくありません。
先輩ママの事例
Dさん:「建築時に数十万円かけて省令準耐火仕様にしたら、火災保険と地震保険合わせて10年で20万円以上節約できました」
補足Point
建物仕様の確認は保険加入前だけでなく、住宅購入時やリフォーム時にも必須。仕様書や管理会社からの情報取得を忘れずに。
地震保険でよくある失敗とは?
Answer
補償の過不足や書類不足によるトラブルが多く報告されています。
Why?
加入時に必要な書類(登記簿、確認済証など)が揃っていなかったり、補償額を過小・過大に設定してしまうことで「いざという時に使えなかった」「無駄に保険料を払いすぎていた」といった事例が多数見られます。また、地震後に申請しようとしても記録が残っていないと保険金請求がスムーズにいかないことも。
先輩ママの事例
Eさん:「申込時に建築確認済証がなくて手続きに2週間かかり、その間に地震が起きて冷や汗をかきました」
補足Point
事前に「地震保険チェックリスト」を作成し、補償内容・金額・必要書類を一覧で整理しておくと安心です。
2025年以降の地震保険料はどう変わる?
Answer
2025年以降、AI細分化と新料率導入により、保険料格差がさらに拡大する見込みです。
Why?
損害保険料率算出機構による最新改定では、南海トラフや首都直下型の影響を考慮し、リスクの高い非耐火住宅で平均7.2%の上昇が見込まれます。また、AIによるリスク評価が始まり、30mメッシュごとに料率が変わる精緻なシステムが導入され始めました。これにより、同じ市区町村でもエリアによって保険料が大きく異なる可能性が出てきています。
補足Point
保険見直しのタイミングは「料率改定の直後」がベスト。長期契約でも途中見直し可能なため、契約内容を見直してみましょう。
FAQ(よくある質問)
Q. 地震保険に加入するのは義務ですか?
A. いいえ、義務ではありません。ただし、住宅ローン契約時に火災保険とのセットで求められることが多いです。
Q. 地震保険だけに加入することはできますか?
A. できません。火災保険に付帯する形でのみ加入可能です。
Q. 家財保険は必要ですか?
A. 家族構成やライフスタイルにより異なりますが、地震時に家具の損害が起きやすいため、多くの家庭で必要とされています。
Q. 保険料は年ごとに変わりますか?
A. 基本的には料率改定時にのみ変更がありますが、長期契約をしていない場合は、毎年更新時に見直されることがあります。
Q. 見直しはどのタイミングでするべきですか?
A. 建て替え・リフォーム・料率改定・家族構成の変化時など、ライフイベントの節目に行うのがおすすめです。
まとめ:地震保険の相場とは?
1. 地震保険の保険料は5つの要素で決まる
地域・建物構造・築年数・保険金額・免責金額が主な影響要素です。
2. 地域や建物構造で保険料は倍以上違うこともある
同じ条件でも北海道と首都圏では2倍以上の差が生じます。
3. 免責設定や長期契約で保険料を節約できる
省令準耐火や5年契約割引を活用するとお得です。
4. 加入前のチェックリスト活用が失敗回避に有効
書類・補償内容・相場比較を事前に確認しましょう。
5. 2025年以降はAIで料率がさらに細分化される
エリアや住宅性能に応じて保険料が大きく変動する時代に突入しています。
地震リスクの高まる今こそ、保険料と補償を見直し、安心できるマイホーム計画を進めましょう。