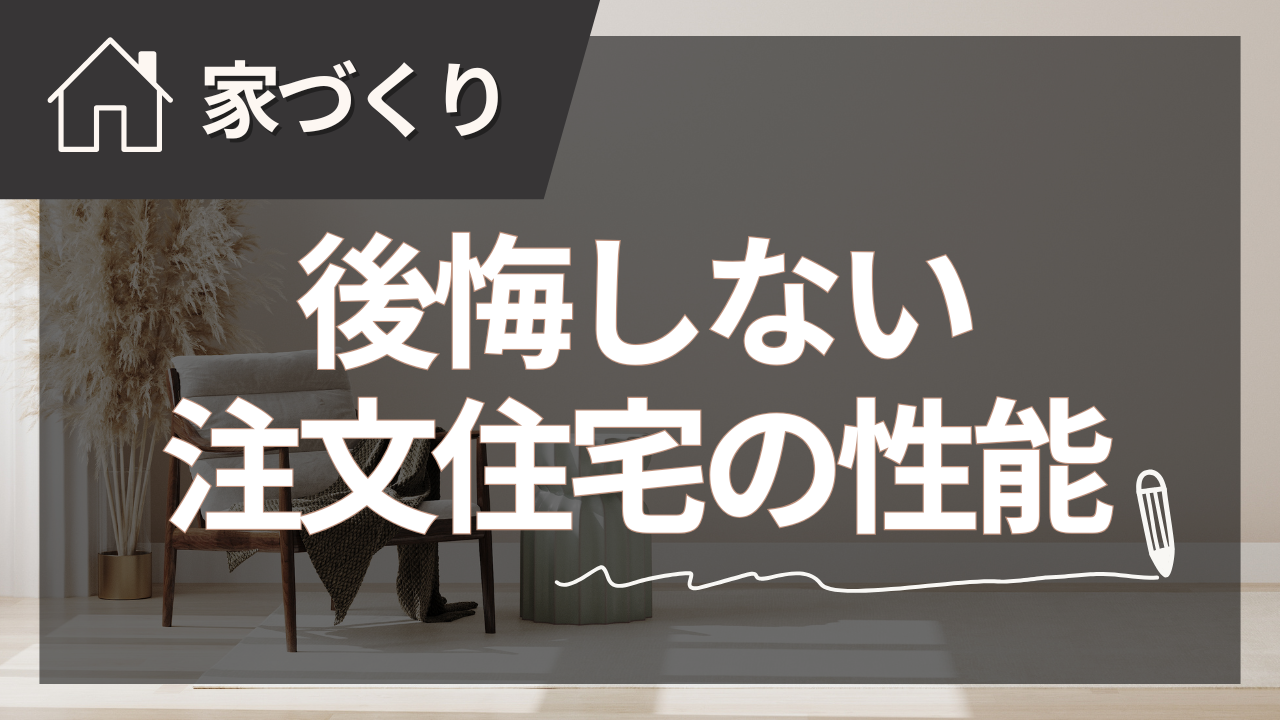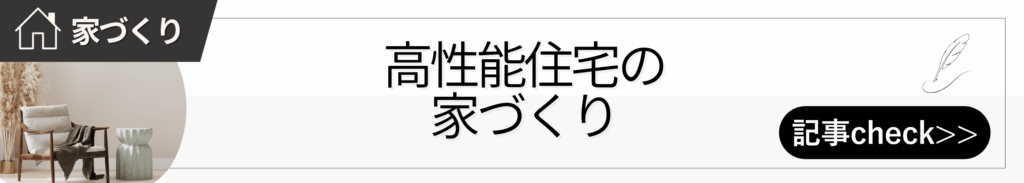注文住宅における性能の基本を知る
注文住宅における「性能」とは具体的に何を指すのか?
注文住宅における「性能」とは、単に快適さだけを示すものではありません。住宅の安全性、耐久性、環境性能など、暮らしを支えるあらゆる要素を含んだ重要な指標です。たとえば、地震に強い家であるかどうかという耐震性、夏は涼しく冬は暖かいという断熱性、冷暖房の効率を高める気密性、建物の劣化を抑える耐久性、そして光熱費を抑える省エネ性など、これら全体をバランスよく備えてこそ「性能が高い家」と言えます。
また、注文住宅ならではの自由設計において、どこにどのように性能を持たせるかは大きな分岐点となります。施主のライフスタイルや地域の気候、予算とのバランスを考えながら、「自分たちにとって最適な性能とは何か?」を最初にしっかり考えることが欠かせません。単に「高性能」を求めるのではなく、「目的に合った性能」を選ぶ姿勢が、後悔しない家づくりの第一歩です。
住宅性能が住まいの快適性・安全性に直結する理由
住宅性能が高ければ高いほど、日々の暮らしにおける快適さや安心感は増していきます。たとえば、断熱性が高い住宅では、外気の影響を受けにくく、一年中温度が安定しやすいため、エアコンに頼らず過ごせる日が増えるでしょう。また、気密性が高いことで、すきま風や騒音、花粉などの侵入も防げ、アレルギー体質の方にも優しい空間になります。
さらに、耐震性を備えた構造は、地震が頻発する日本において必要不可欠です。災害時に家族の命を守れるかどうかは、こうした見えない部分の性能にかかっています。つまり、性能は単なる“数字”や“仕様書上の項目”ではなく、暮らす人の「日常」に直接影響を与える重要な要素なのです。家族の健康や安心を守る基盤こそが、住宅性能の本質と言えるでしょう。

注文住宅の性能で重視すべき5大要素とは
耐震性能|地震に強い家づくりの第一歩
耐震性能は、地震大国である日本において最も基本的かつ重要な住宅性能の一つです。注文住宅を検討する際には、建築基準法の最低限の耐震性(耐震等級1)を満たすだけでなく、できれば「耐震等級2」や「耐震等級3」を目指すべきです。これらは災害時の避難所に求められるレベルの強度を示しており、地震が来ても倒壊しにくい構造であることを意味します。
加えて、建物の形状や間取り、基礎構造、使用する建材なども、耐震性能に大きく関わります。たとえば、1階部分がガレージで開口が大きい家や、吹き抜けが多い設計では、構造的な強度が低くなることもあります。見た目や間取りの自由度に偏りすぎず、構造計算をしっかり行ったうえで設計することが大切です。
設計段階から「構造計算が入るかどうか」を確認し、地震に備える家づくりを意識して進めていきましょう。
断熱性能|一年中快適に過ごすための基本
断熱性能とは、外気温に影響されにくい室内環境を実現するための性能であり、冷暖房効率にも大きく関係します。夏は涼しく、冬は暖かく保つことで、快適な住環境を保ちつつ、光熱費の削減にもつながります。
住宅の断熱性を左右するのは、主に断熱材の種類と施工の丁寧さ、そして開口部(窓やドア)の仕様です。最近では、吹付けウレタンや高性能グラスウールなど、高断熱な素材が普及していますが、どれを選ぶかよりも、隙間なく施工されているかが重要です。また、断熱等性能等級という指標もありますので、目安として等級4以上を基準にするとよいでしょう。
窓ガラスは複層ガラスやLow-Eガラス、樹脂サッシを採用することで、より高い断熱効果が期待できます。エネルギー効率の良い家づくりには、断熱性能の高さがカギを握っていると言えます。
気密性能|冷暖房効率と健康に影響する重要ポイント
気密性能とは、住宅の隙間の少なさを示す性能で、断熱性能と並んで快適な住空間の実現に欠かせません。家に隙間が多ければ、どんなに良い断熱材を使っても外気の影響を受けやすく、冷暖房の効率も悪くなってしまいます。結果として、エネルギーの無駄が生まれ、光熱費もかさみます。
また、気密性の高い住宅は、花粉や黄砂、PM2.5などの外部汚染物質の侵入も防ぎやすく、喘息やアレルギーを持つ家族にも安心です。さらに、気密性が高いことで換気計画も正しく機能し、結露やカビのリスクを減らすことができます。
気密性能は「C値」という数値で評価され、値が小さいほど性能が高いとされます。高気密高断熱住宅を謳う場合は、C値1.0以下を一つの基準にするとよいでしょう。見えない部分だからこそ、施工会社の実績や気密測定の有無も要確認です。
耐久性能|長く住み続けるために欠かせない視点
家は一度建てたら何十年も住み続ける場所です。そのため、長期的に劣化しにくく、メンテナンスコストを抑えられる「耐久性能」は非常に重要です。耐久性能が高い住宅は、構造材や外壁材、屋根材の選定はもちろん、湿気対策、シロアリ対策、防水処理など、多面的な視点から評価されます。
たとえば、耐腐食性に優れた金属屋根や、セルロースファイバーのような調湿機能のある断熱材などを取り入れることで、構造の寿命が延び、住まいの劣化を遅らせることができます。さらに、基礎部分の通気設計や床下環境の管理も耐久性に大きな影響を与えます。
見た目の新しさだけでなく、20年後、30年後も快適に住み続けられるかという視点を持ち、家の構造や仕様を検討することが大切です。注文住宅だからこそ、ライフステージの変化を見据えた耐久設計が求められます。
省エネ性能|光熱費を抑えて環境にも配慮
近年注目されているのが、省エネ性能です。電気代やガス代が高騰する中、エネルギー効率の良い家は家計に優しく、環境負荷の軽減にも貢献します。注文住宅では、高性能な断熱・気密性に加え、省エネ設備の導入が欠かせません。
具体的には、太陽光発電システムや蓄電池、エコキュートなどの導入が挙げられます。また、家庭で消費するエネルギー量を評価する「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」などを参考にすることで、客観的に住宅の省エネ性能を判断できます。
最近では、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)を目指す住宅も増えています。これは、自家発電と高断熱・高気密仕様により、エネルギー収支が実質ゼロになることを目指した住宅です。未来を見据えた省エネ住宅は、快適さと持続可能性の両立を図る上で大きな価値があります。

注文住宅の性能評価制度とその見方
「住宅性能表示制度」とは?国が定める客観的な指標
住宅性能表示制度は、住宅の性能を国が定めた共通の基準で評価する仕組みで、消費者にとって重要な判断材料となります。この制度では、耐震性・耐風性・断熱性・遮音性・劣化対策・維持管理など、10項目にわたる性能を等級や数値で表示します。
たとえば「耐震等級3」は、最高レベルの耐震性を示しており、災害時の避難所基準を満たす設計です。また、「断熱等性能等級」では、数値が高いほど断熱性能が高く、省エネ性にも優れていることが分かります。
この制度を利用することで、住宅会社の言葉だけでは判断しづらい性能の違いを、数値で比較することが可能です。注文住宅を検討する際は、性能表示がされているか、どの等級を目指すかを確認しながら計画を立てましょう。
BELS、長期優良住宅、ZEH認定など各種制度の違い
住宅の性能を判断するうえで、BELS(ベルス)、長期優良住宅、ZEHなど複数の制度があります。それぞれ目的や評価基準が異なるため、混同せずに理解することが大切です。
BELSは、省エネ性能を星1〜5で評価する制度で、建築物のエネルギー効率を見える化します。長期優良住宅は、構造の劣化対策や省エネ性、維持管理の容易性などを含め、長く快適に住める住宅であることを国が認定します。一方、ZEHはエネルギー収支をゼロ以下にする住宅で、断熱・省エネ・創エネの三位一体で評価されます。
どの制度を重視するかは、ライフスタイルや将来の資産価値の考え方によって異なります。補助金制度との関係性もあるため、認定を受けることで金銭的メリットも期待できます。
評価制度をどう読み解く?見るべき指標と注意点
性能評価制度は非常に便利ですが、すべてを鵜呑みにするのではなく、見方を理解することが重要です。たとえば、同じ「耐震等級3」でも、木造と鉄骨では設計思想や構造が異なります。また、評価はあくまで計画時点での基準であり、実際の施工精度が伴っていなければ意味がありません。
評価制度を活用する際には、評価内容の中でも「等級の根拠となる設計図」「使用する材料」「施工体制」まで確認することが理想です。さらに、第三者機関による現場検査の有無や、完成後の性能試験なども住宅性能の裏付けとして注目すべきです。
注文住宅の性能をどう比較・判断すべきか
カタログや営業トークに惑わされないチェックポイント
注文住宅を選ぶ際に注意したいのが、パンフレットや営業担当のトークだけで判断しないことです。性能に関する表現は「高気密・高断熱」や「耐震等級3」など耳障りの良い言葉が並びますが、それが実際にどのような根拠をもとに語られているのかを確認する必要があります。
たとえば、「断熱性能が高い」と言われたら、その断熱材の種類や厚み、施工方法を具体的に聞いてみる。また、「耐震性に優れる」と説明されたら、構造計算を行っているか、耐震等級はいくつか、制震装置の有無などを確認しましょう。
加えて、性能表示における等級の取得状況、第三者機関の検査の有無などもチェックポイントです。パンフレットのビジュアルに安心せず、実際の数値や実例、実績をもとに比較・判断していく姿勢が重要です。
性能の数値化とその落とし穴
住宅性能は「数値化」できるものが多く、耐震等級やC値、UA値などは重要な判断材料となります。しかし、数値だけにとらわれると、本質を見落とすリスクもあります。
たとえば、UA値(外皮平均熱貫流率)は断熱性能を示す重要な指標ですが、気密性や換気設計が悪ければ実際の快適さは確保できません。また、断熱材の厚さだけで性能を語るのは危険で、施工不良や結露リスクが潜んでいるケースもあります。
つまり、性能の「実効性」を確認するには、数値だけでなく、設計と施工の一体性、現場での品質管理、実際に住んでいる人の声など、多角的な視点が求められます。数値は目安として活用しつつ、「なぜその数値が出せているのか?」を深掘りして判断しましょう。
実物を見ることが重要な理由|モデルハウスの活用法
どれだけカタログや説明を見聞きしても、最終的にその性能が「肌で感じられるかどうか」は、実物を見ることでしか分かりません。モデルハウスや完成見学会は、住宅性能を体感できる貴重な機会です。
特に断熱・気密性能の高さは、室内の空気感や温度のムラのなさで体感できます。また、窓やサッシの仕様、床下や小屋裏の断熱材の施工状態を見せてもらうことで、施工の丁寧さも確認できます。高性能住宅を謳う場合、実物で確認できる場を用意しているかどうかも信頼のポイントになります。
加えて、住んでいる人の声を聞ける「入居者宅訪問」などの機会があればぜひ参加しましょう。数値だけでは分からない「暮らしの実感」が得られるはずです。

性能の高い注文住宅を建てるための設計と施工のポイント
性能を最大限に引き出す間取りと断熱設計
高性能住宅を実現するには、素材や設備だけでなく「設計の工夫」が重要です。たとえば、日射をコントロールするための窓の配置や軒の出、通風を考慮した開口部の設計は、自然エネルギーを活かしながら性能を引き出す基本になります。
また、断熱性能を最大限に活かすためには、家全体を断熱材で“包み込む”外皮計画が必要です。床下、壁、天井、サッシに至るまで連続した断熱ラインを確保し、断熱欠損が出ないよう設計段階から配慮することが求められます。
つまり、「デザイン先行」ではなく「性能と暮らしを両立させる設計」が最も重要です。設計士のスキルによって大きく結果が変わるため、提案力のある設計パートナーを選びましょう。
性能を落とさない施工品質の見極め方
性能設計が完璧でも、現場施工の質が低ければその性能は発揮されません。たとえば、断熱材がずれて施工されていたり、気密処理が甘かったりすると、設計上の性能とはかけ離れた家になってしまいます。
そこで重要になるのが、現場監督の管理体制や職人の技術力です。性能重視の住宅会社であれば、気密測定(C値測定)や断熱材の施工検査などを第三者機関に依頼し、品質を“見える化”してくれるところもあります。
施主側も、建築中に現場を見学したり、構造見学会に参加することで、現場の対応力や丁寧さを見極めることができます。「家は現場でつくられる」という意識を持ち、設計と施工のバランスを重視しましょう。
住宅会社選びで失敗しないための基準
住宅性能を最大限に引き出すには、会社選びも極めて重要です。どんなに素晴らしい性能設計があっても、実現力がなければ意味がありません。
判断基準としては、「性能表示制度への対応」「断熱・気密測定の実施」「現場見学の機会」「社員や設計士の知識レベル」「施工実績」「入居者の声」などを総合的にチェックしましょう。また、断熱性能や気密性能を数値で提示してくれる会社は信頼性が高いです。
「デザインが好み」「営業の人が感じが良い」などの印象も大切ですが、家の基本性能がなければ暮らしの満足度は上がりません。住宅会社選びでは、見た目ではなく中身を重視することが、失敗しない家づくりのカギとなります。
補足Point
下記コラムも、ぜひ併せてご覧ください。

性能の高い家を建てるために知っておきたいこと
家づくりを始めると、気になることが次々と出てきます。
ネットで情報を調べても、「これって本当に正しいの?」「うちに合ってるのかな?」と、かえって不安になる方も少なくありません。
そんな悩みに寄り添うために、私たちはNo.1住宅プランナーと、家づくりを経験した先輩ママたちと一緒に、“日本一信頼できる家づくりプラットフォーム”をつくりました。
▼後悔のない家づくりのために、まずは気になることから、ゆっくり見てみませんか?